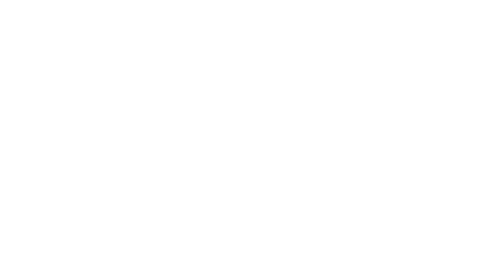『今日の下着は、倫くんが好きなやつだよ』
その一文で、世界がバグった――
春の風が頬を撫でる夕暮れ時、稲荷崎高校の校門を抜けた瞬間、柔らかな陽光が視界を金色に染めた。木々の間を抜ける光が地面に斑な影を落とし、俺のスニーカーの先を淡く照らす。スマホを片手に歩きながら、頭の中では今日の練習の残響が鳴り続けていた。体育館に響くボールの乾いた音、チームメイトの鋭い掛け声、汗と埃が混じる空気――身体は心地よい疲労に包まれていたが、今の俺の意識は別の場所に囚われていた。
「倫くん」
背後から響いた声に、俺は足を止めて振り返る。夕陽を背にした名前がそこに立っていた。艶やかな髪が風にそよぎ、陽光を透かして縁取られたその姿は、まるで絵画のようだ。白い肌が光を跳ね返し、深い瞳が俺を静かに捉える。無機質で感情の読めないその眼差しは、人形めいた冷たさを漂わせるが、唇に浮かぶ微かな笑みがその印象を溶かしていた。
「お疲れ様」
名前の声は、春の小川のように穏やかで澄んでいる。
「名前ちゃん、待っててくれたの?」
喉から出た言葉が、いつもより少し柔らかく響いた気がした。
「うん。倫くんに会いたかったから」
さらりと名前が答える。その自然さは、空気が揺れるような軽さだ。なのに、俺の胸の奥で何かが跳ねた。
「……そっか」
何気ないやり取りの筈なのに、心臓が不規則に鳴る。理由は単純で、馬鹿みたいに明白だ。
(こいつ、可愛過ぎる)
名前が一歩近づき、俺を見上げる。夕陽が彼女の瞳に反射し、夜の海に星が瞬くような輝きを宿していた。
「倫くん、マスクをしているんだね」
「ああ、まあね。花粉が凄いし」
口から滑り出た言い訳は、薄っぺら過ぎて自分でも笑える。勿論、嘘だ。本当の理由は、練習後の部室で、名前からのメッセージを開いた瞬間にある。
『今日の下着は、倫くんが好きなやつだよ』
その一文が目に飛び込んだ時、頭の中で何かが爆発した。顔が熱くなり、耳まで火照るのが分かった。慌てて、スマホを握り潰しそうになりながらスクロールすると、追い打ちを掛けるように写真が現れる。ベッドに寝転んだ名前が、制服の裾をほんの少しだけ捲り上げた姿。黒いレースが白い肌に影を落とし、隠れている部分を逆に際立たせていた。全てが見えているわけじゃない。だが、その曖昧さが逆に脳を直撃した。
「ヤバい」と口に出してしまい、周囲の視線を気にして、慌ててマスクを引っ張り出した。あの写真を見た後、名前の顔をまともに見られる自信がなかった。動揺を隠す為の、情けない防壁だ。
「倫くん、ちょっと赤いよ」
名前の声が、現実を引き戻す。彼女の瞳が俺の顔を覗き込み、微かに首を傾げる。
「……気のせいだよ」
平静を装って返すが、声が微かに震えた。頬の熱がマスク越しにも伝わりそうで、視線を逸らす。
「そうかな?」
名前が一歩踏み込み、俺との距離を詰める。風が彼女の髪を揺らし、ミントと桜が混ざったような香りが鼻先を掠めた。
(近い)
透き通る肌、深い瞳、淡く色づいた唇。こんな距離で名前を見つめると、心臓が喉元までせり上がる。冷静でいられるわけがない。
「倫くん、マスクを取って?」
「……無理」
反射的に拒否が口を衝く。声が硬くなり、指先が汗で湿る。
「どうして?」
「顔、見られんの困るから」
喉が締まり、言葉が詰まった。名前の瞳が俺を捉え、逃げ場がない。
「ふふ……どうして困るの?」
名前の声に、かすかな笑みが混じる。彼女の指が俺の肩に触れ、軽く爪先で制服を引っ掻くような仕草をする。
――ああ、こいつ。わかっててやってるな。
「……あんまり、俺を揶揄うなよ」
声が低くなり、警告のつもりで言った。だが、名前の瞳に浮かぶ遊び心を見ると、それが無意味だと悟る。
「揶揄っていないよ。本当のことを知りたいだけ」
名前の手が伸び、マスクの縁に白い指先が触れた。彼女の爪が軽く引っ掛かるる感触が、耳元でかすかに音を立てる。
――ヤバい、やばい。
「……名前ちゃん」
名前を呼ぶ声が掠れた。彼女の指が止まり、俺を見上げる。
「倫くん、ダメ?」
「ダメって言うか……」
言葉が途切れる。名前の瞳に宿る期待が、俺の抵抗を溶かす。
「倫くんが隠している顔、見たい」
「……俺、今、滅茶苦茶ヤバい顔してる」
自嘲気味に呟く。頬が熱く、耳まで火照っているのが自分でも分かる。あの写真を思い出しただけで、顔が制御不能だ。
「……だから見たい」
名前の声が低く、密やかに響く。彼女の指がマスクの紐に掛かり、ゆっくりと引き下げる。
――もう逃げられない。
「……わかった。後悔しないでよ?」
「しないよ」
彼女の言葉に頷き、俺は目を閉じた。マスクが外れる瞬間、春の風が頬を撫で、熱を持った肌に冷たい感触を残す。顔が露になり、名前の視線が俺を捉えた。
「……倫くん、凄く赤い」
「……言ったじゃん」
彼女の声に、微かな驚きと喜びが混じる。頬が熱い。完全に自爆している自覚はある。あのメッセージと写真が頭を支配し、名前を想像してしまった自分が情けない。
「倫くん、顔が火照ってる」
名前の手が俺の頬に触れ、指先が軽く肌を撫でる。その感触に、全身の神経が鋭敏になる。
「……しょうがないじゃん」
声が低く掠れた。言い訳じみているが、本音だ。
「どうして?」
「……さっきのメッセ」
「ああ、あれ?」
名前の声に、悪戯っぽい響きが混じる。
「"あれ"って、なあ……」
抗議の言葉が喉で詰まる。名前の瞳が俺を捉え、逃げ場がない。
「ふふ……倫くん、想像した?」
「……するに決まってるだろ」
正直に答えた瞬間、名前の指が俺の頬を軽く摘む。柔らかな感触が、熱を帯びた肌に心地よい。
「倫くんがそんな風に考えるなんて、可愛い」
名前の声が耳元で響き、俺の心臓が更に跳ねる。彼女の手が頬から首筋に滑り、その温度がシャツの襟を越えて伝わった。
「倫くん、キスしてもいいよ」
「……誘ってる?」
「うん」
名前の瞳が細まり、唇が微かに開く。その一言に、理性が揺らぐ。
――どうする?
ここで我慢すべきか? いや、無理だ。こんな可愛い顔で「いいよ」と言われて、理性が保てる男が居たら尊敬する。
あの写真が頭にチラつき、彼女の香りが鼻腔を満たす。もう限界だった。
「……ほんと、ズルい」
呟きながら、俺は名前の手を取った。彼女の指が俺の掌に絡み付き、その温もりが心を溶かす。そっと彼女を引き寄せ、唇を重ねた。
触れた瞬間、名前の瞳が細まり、微笑みが広がる。柔らかな唇の感触が、俺の全身に電流のように走った。彼女の息が俺の頬を掠め、淡い甘さが混じる。
「倫くんが、マスクを取って良かった」
名前の声が囁きのように響く。彼女の手が俺の肩に触れ、軽く爪先で制服を掴む。
「……名前ちゃんの所為だし」
「でも、倫くんがわたしをそんな風に思っているってわかって、嬉しかった」
彼女の瞳が俺を捉え、その奥に純粋な喜びが宿る。俺の胸が締め付けられ、言葉が喉で詰まった。
「……あんまり、俺を揶揄うなって」
「うん。でも、もっと知りたい」
名前の声が耳元で反響し、俺の心を揺さぶる。彼女の手を強く握り、もう一度、抱き寄せた。彼女の髪が俺の頬を擽り、その感触が現実を確かなものにする。
「もう無理。今度は、俺が後悔させるから」
低い声で呟き、彼女の首筋に顔を寄せる。名前の香りが鼻腔を満たし、俺の心を完全に捕らえた。彼女が小さく笑い、俺の腕の中で静かに身を預ける。
校門の外、夕陽が地平線に沈む頃、俺は悟った。――この恋は、名前に主導権を握られている。でも、それでいいと思ってしまう自分が居ることも、もう認めざるを得なかった。彼女の微笑みが俺を包み、春の風が二人を優しく撫でていった。