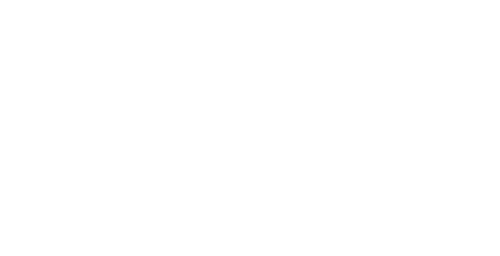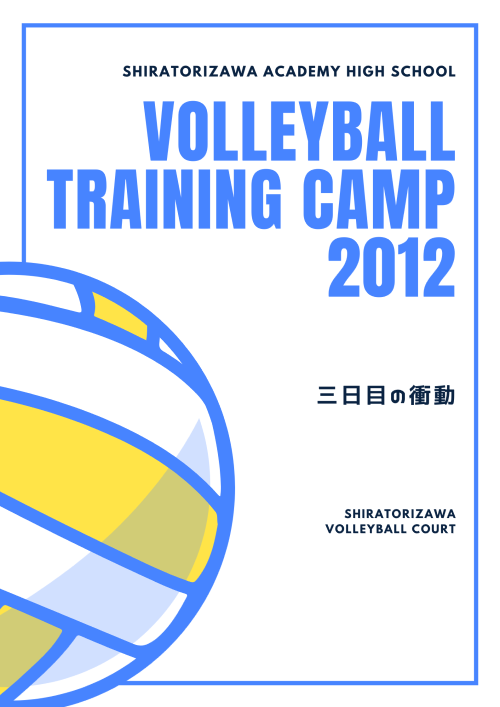
じりじりと照り付ける太陽がグラウンドの乾いた土を容赦なく焼き、陽炎めいた匂いを立ち上らせている。白鳥沢の校章が誇らしげに縫い付けられたネットに、熱を含んだ風が気紛れに絡み付き、今日の練習もまた一筋縄ではいかないだろうと無言の内に告げていた。合宿も三日目。身体は過酷なスケジュールに順応し始めている筈なのに、鉛を飲み込んだような疲労感が抜け切らず、肩から腕に掛けてが妙に重怠い。
白布賢二郎は温くなったスポーツドリンクを飲み干すと、スクイズボトルを片手に体育館の出入り口近く、壁が作る僅かな日陰へと一人腰を下ろした。ぎらつく光から逃れるように目を細める。
「……ったく、底なしかよ」
視線の先、体育館の中では、天童と五色が子供のようにボールを取り合って――と言うか、天童が一方的にじゃれている。その直ぐ横では、タオルで首筋の汗を拭いながら、瀬見が「お前ら! 少しは静かにできねぇのか!」と、やや呆れたような声で叫んでいた。いつもの光景。白鳥沢学園高校男子バレーボール部の、日常の一コマ。
――喧しい。
だが、その感情は単純な苛立ちではなかった。ましてや、彼らのエネルギーに対する羨望でもない。それは寧ろ、合宿中の自分にとって決定的に欠けている"何か"に対する、静かで、それでいて無視できない焦りのようなものだった。喉の奥に痞えた小骨のような、ざらついた感覚。
合宿中は当然、携帯電話やスマートフォンの使用が厳しく制限されている。許されるのは、合宿所に戻ってからの僅かな自由時間のみ。
彼女――苗字名前に、自由に連絡を取ることができないこの状況は、白布が当初想定していた以上に、じわじわと精神を蝕んでいた。たった数日。されど数日。彼女の声を聞けない、日中はメッセージ一つ送れないという事実が思考の端々に影を落とす。
白布は一つ深く息を吸い込み、背後にある、ひんやりとしたコンクリートの壁を見上げた。無機質なその表面に、自分の内面が映し出されるような気がした。
(名前……今頃、何してるんだろうな)
意識がそちらへ向かう度、脳裏には鮮明に彼女の姿が浮かび上がる。陽の光を吸い込むような白い肌、吸い込まれそうな程に深い色の瞳。ふとした拍子に見せる、花が綻ぶような、けれど、どこか儚げな笑み。そして、自宅のグランドピアノに向かう時の、鍵盤の上を滑るしなやかな指先の動き。
そして、思考は必然的に、ほんの数日前の出来事へと遡る――あの、名前の部屋での一幕。
「お前、そんな下着つけてるとか、不埒だろ……」
ぽつりと、自分でも意図せず漏れた言葉が、今になって生々しく耳の奥で再生される。白布は思わず眉間を押さえた。熱い記憶が蘇り、耳朶がじんと熱くなる。
あれは確か、自主的に行っているロードワークの合間、偶然を装って通り掛かった名前のマンションに、ほんの少しだけ、という口実で立ち寄った時のことだ。タイミング良く、あの掴みどころのない兄の兄貴が不在だと聞き、張り詰めていた緊張の糸がふっと弛んだ白布は、つい何の躊躇もなく、彼女に背後から抱き付いてしまったのだ。普段なら、もう少し理性が働く筈なのに。
名前は特に驚いた様子も見せず、ただ静かに振り返って、「……賢二郎、また抱き締めているの?」と、子供に言い聞かせるような、穏やかな声で問い掛けた。
その瞬間、彼女が着ていた、少しゆったりとしたブラウスの襟元が僅かにズレて、華奢な肩のラインと共に面積の少ない繊細なレースが覗いたのだ。淡い、上品な色の――
「……ッ、考えるな」
ガシッと自分の頭を両手で掴み、白布は誰に聞かせるともなく小さく呻いた。駄目だ、今は。合宿中だ。俺は白鳥沢の正セッターだ。コートの中では冷静沈着でなければならない。牛島さんを筆頭に、チームを勝利へ導く責任がある。今この瞬間も、鷲匠監督がどこかで見ているかもしれない。そんな時に女子の、それも下着のことなんか考えている場合じゃない。
それでも思考というものは、意志の力だけでは都合よく制御できるものではないらしい。
あの時の、ほんのりと紅潮していた名前の頬。耳元で囁いた自分の声の掠れた響き。そして、衝動的に絡めた指先の柔らかさと熱。白布はごくりと渇いた喉を鳴らした。心臓が嫌な音を立てて脈打つ。
(……不埒、なのは、どう考えても、俺の方だ)
完全にアウトだ。自覚はある。名前に触れたい。もっと近くで、彼女を感じたい。今直ぐにでも。何なら、合宿所をこっそり抜け出してでも会いに行きたい――そんな、突拍子もない考えまで頭を過る。
「……いや、待て」
ぶんぶんと激しく頭を左右に振る。セッターがこんなことで集中力を欠いてどうする。これからまた厳しい練習が待っている。チームメイトからの信頼に応えなければならない。俺が、チームの、牛島さんの力を最大限に引き出すんだ。
だが、必死で邪念を振り払おうとすればする程、皮肉にも彼女の言葉が鮮明に蘇ってくる。合宿に出発する前日、少し寂しそうに、けれど強い意志を込めて言われた言葉。
『わたしのこと、合宿中も忘れないでね』
(忘れられるわけ、ないだろ……)
胸が締め付けられるような、切ない感覚。白布にとって、名前の存在は最早、単なる恋人という枠を超えて、自身の精神的なバランスを保つ上で不可欠なものになりつつあった。それを、この物理的な距離が改めて突き付けてくる。
再び体育館の中から、五色の唯一の取り柄である大声が飛んできた。
「白布さーん! 休憩終わったら、トスお願いしますー!」
そちらへ顔を向けると、五色の隣で天童が何かを耳打ちして笑っていた。恐らく、また五色の前髪についての話題だろう。
その時だった。不意に自分の頭上に、それまでよりも一層濃い影が落ちた。そして――見慣れた、絹糸のように細く艶やかな髪が、強い陽射しを遮るようにふわりと揺れた。
「……は?」
思考が完全に停止した。いや、そんな筈は、ない。だって、名前は帰宅部で、今頃は家族と過ごしている筈で、ここは白鳥沢学園の敷地内で、今は連休を利用した強化合宿の真っ最中で――
けれど、そこに居たのは紛れもなく。学校指定の清楚なブラウスに、品の良い紫色のチェックのスカート。まるで蜃気楼のように、しかし、確かな実体を持って、冷たい影を背負いながら、苗字名前が静かに立っていた。
「……えっ、名前……?」
何故。どうして。ここは男子バレー部の体育館前だぞ? 関係者以外、用はない筈だ。
呆然と立ち尽くす白布の前で、名前はいつものように僅かに首を傾げ、その大きな瞳でじっと彼を見つめて言った。
「……忘れないでって言ったのに、考えてくれていない顔だったから」
「いや、逆だ……考えてた。寧ろ、考え過ぎて、頭がおかしくなりそうだった……」
掠れた声で答えると、名前はふっと表情を和らげた。
「じゃあ、大丈夫だね」
そう言って微笑んだ彼女の目は、相変わらず深海のようにどこまでも深く、容易には底を見せない。だが、白布には、その静かな眼差しの奥に揺らめく、柔らかな、しかし、確かな愛情の熱を誰よりもはっきりと感じ取ることができた。
「兄貴兄さんには、図書室で勉強するって言ってある」
「……は? ここ、体育館前だぞ」
「うん、知っている。賢二郎が毎日、凄く頑張っていることも。……だけど、ほんの少しだけ、顔を見るくらいなら、許されるかなって思ったの」
それは余りにも無防備で、余りにも突拍子がなく、そして、余りにも名前らしい理屈だった。常識やルールよりも、自分の"想い"を優先する。その危うさが、白布を惹き付けてやまない理由の一つでもあるのだが。
「監督とか、他の人に見られたら――」
言い掛けた白布の言葉を遮るように、名前は彼の背後を視線で示した。
「そこに立っている人、監督さんでしょう?」
白布が弾かれたように振り返ると、そこには腕を組み、仁王立ちになった鷲匠監督の姿があった。いつからそこに居たのか。無表情のまま、じっとこちらを見つめている。その視線は全てを見透かしているかのようだ。
全身から、ぶわっと冷や汗が吹き出した。終わった、と思った。怒鳴られるか、最悪、合宿から追い出されるか――覚悟を決めた、その瞬間。
「賢二郎」
低く、しかし、体育館の喧騒の中でもよく通る声が響いた。
「戻るぞ。昼にしらす食って目を覚ませ」
「……はい、すみません」
予想外の展開に、白布は裏返りそうな声で返事をするのが精一杯だった。一言だけ。それで終わり。怒声も、罰も、何もなかった。
けれど、白布には痛い程に分かっていた。あの鷲匠監督の、或る意味で"締めの一声"が、最大限の、そして恐らくは最初で最後の慈悲だったということが。あの人はきっと気づいている。自分が今、どんな状態にあるのか。そして、この突然の訪問者の意味も。
体育館内に戻る前、彼は周囲の目を盗むようにして、名前の手をほんの一瞬だけ、強く握った。彼女は驚くでもなく、ただ静かに、その温かい手を握り返した。
「不埒なことは、暫くお預け……かな」
名前の言葉は囁くように小さかったが、白布の胸に直接響いた。その声の奥にある約束に、彼の心は早鐘を打つ。
「……次会った時、覚悟しといて」
白布の言葉は、いつもの静かさとは違う色を帯びていた。自分でもそれを感じ、耳まで熱くなる。
「うん」
その返事と共に浮かべられた、はにかむような微笑み。そして、見る見るうちに彼女の白い頬が、耳までが、淡いピンク色に染まっていくのを、白布は見逃さなかった。その表情だけで、あと数日の合宿は乗り切れそうな気がした。
体育館の中に入り、彼は一度だけ振り返った。名前の姿はもうそこになかった。まるで幻だったかのように消え去っていた。だが、手のひらに残る温もりは確かに実在していた。
その晩、消灯後の合宿所の大部屋で、白布は日記帳に走り書きのような短い一文を記した。綺麗な字で、しかし、少し震えた筆跡で。
【2012年某月某日】
合宿三日目。名前、来た。突然の訪問。
鷲匠監督、何故か優しかった。
手、温かかった。柔らかかった。
次は、もっと長く。もっと深く触れたい。絶対に。
布団に横たわりながら、白布はもう一度、日記を見返した。言葉には出せない想いが、この短い文章の隙間に潜んでいる。
――我ながら、不埒だ。思考が、願望が、止まらない。
だが、恋とはきっと、そういうものなのだろう。理屈や理性など、いとも簡単に吹き飛ばしてしまう、抗い難い衝動そのものなのだから。
明日は練習試合。頭は冴えていなければならない。だが、今夜だけ、彼は名前の記憶に浸ることを自分に許した。闇の中で、彼女の姿がぼんやりと浮かび上がる。それだけで充分だった。
合宿も、あと三日。彼女に会えるまで、あと三日。