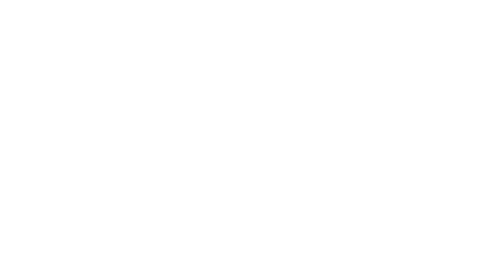俺、佐久早聖臣がマスクを外すのは、限られた場所だけだ。自室、家族の前、そして――名前と二人きりの時。
「今日は、ずっと着けているんだね」
放課後、マンションのエントランスを抜け、エレベーターの扉が閉まると同時に、名前が小首を傾げた。彼女の視線が俺の顔を捉え、眉間に細い皺を寄せる。普段なら、こういう時、俺はマスクを外す。清潔な環境で、誰の目もない空間なら問題ないからだ。でも今日は違う。
「……風邪予防」
適当に答えながら、無意識に指先でマスクの端を引っ張る。緊張で乾いた喉を、唾を飲み込むことで潤した。名前はふぅん、と小さく息を漏らし、俺の腕を掴んだ。その細く、ひんやりとした指先が俺の手首に絡むと、心臓が不規則なリズムを刻み始める。
「臣くん、嘘」
「は?」
「風邪予防なら、授業中もしているでしょう」
真っ直ぐな視線。逃げ場のない鋭さに、俺は無意識に喉を鳴らした。こういう時、名前は容赦がない。追求の手を緩めないのが彼女の性分だ。教室の窓から差し込んだ午後の光の中で、彼女の横顔を見つめていた自分を思い出す。髪が風で揺れる度に、甘い香りが漂ってくる。その度に胸が締め付けられる感覚があった。
「……別に、問題ないだろ」
「あるよ」
ぴたり、とエレベーターが停止する。数字のディスプレイが最上階を示している。扉が開いた瞬間、名前は俺の手を引いてマンションの廊下を歩き出した。無機質なタイル張りの通路に、俺達の足音だけが静かに響く。普段なら気にも留めないその音が、今日はやけに長く、そして、遠く感じる。
鍵を開ける音。微かな花の香り。名前のマンションには、彼女と年の離れた兄しか居ない。今日は兄が出張で不在だと聞いていた。余計な視線がないことに、俺は少しだけ安堵する。だが同時に、緊張感も高まる。
リビングのソファに腰を下ろすと、名前が俺の前に立った。窓から差し込む夕暮れの光が、彼女の輪郭を金色に縁取る。
「外して」
「……何を」
分かっているのに、わざと聞き返す自分が情けない。
「マスク」
拒めないのは、彼女が恋人だからだ。名前の指がゆっくりと伸び、俺の頬に触れる。温かくて、柔らかい。そのまま耳の後ろに掛けられたゴムを外そうとする仕草に、俺は喉がひりつくような感覚を覚えた。鼓動が早くなる。
「自分で、外す」
言いながら、躊躇いがちにマスクを外す。指先が微かに震えているのが自分でも分かる。
――視線を逸らしたかった。いや、逸らすべきだった。
マスクの下、熱を持った肌を晒すのが恥ずかしい。たったこれだけのことなのに、心の奥底まで覗かれるような錯覚に陥るのは、名前が特別だからだ。彼女の前では、どんな防壁も意味をなさない。
「臣くん、顔が赤い」
名前の声は静かだが、その言葉は部屋中に反響するように感じる。
「……気の所為」
「ふぅん」
否定の言葉は、空虚に響く。
ソファに座る俺の膝に、名前が静かに腰を下ろす。髪がさらりと流れ、俺の肩に掛かる。その瞬間、体温が数度上がった。彼女の重さ、温もりが、現実感を持って迫ってくる。
「臣くん、今日はずっと、わたしのことを見ていたね」
思いも寄らない一言に、言葉が詰まる。朝のHRから放課後まで、無意識の内に名前を追っていた視線。窓際の席で、光を浴びて輝く彼女の横顔を見つめていた時間。誰にも気づかれていないと思っていたのに。
「……別に」
「本当?」
悪戯っぽく微笑んだ名前の手が、俺の頬を撫でる。人混みが嫌いな俺が、彼女に触れられることだけは嫌じゃない。それどころか――触れられることを待ち望んでいる自分が居た。普段なら許さない距離感を、彼女だけには許してしまう。
「マスクを外していると、落ち着かない?」
「……お前が近過ぎる」
言葉とは裏腹に、俺の手は自然と彼女の腰に添えられていた。
「それは関係ないと思う」
名前がゆっくりと顔を近づける。その双眸は、夜の海のように深く、俺の思考を攫っていく。瞳の中に映る自分の姿が、少しずつ大きくなる。
――触れたい。
そんな衝動が、抑え切れずに溢れそうになる。マスクが無い今、表情を隠す術はない。
マスクで隠せないものがある。息遣いも、熱も、視線の揺らぎも。それらすべてが、今の俺の内側で渦巻いている感情を物語っている。
名前の唇が、触れそうな距離まで近づいた。彼女の吐息が俺の肌を撫で、微かな甘さを含んだ香りが鼻腔を擽る。その香りは、俺の理性を溶かす媚薬のようだ。
「臣くん」
名前を呼ばれた瞬間、世界が一瞬止まったように感じた。
彼女の目には、俺だけが映っている。その事実が、胸の奥を熱くする。
俺はもう、抗えなかった。
手のひらで彼女の頬を包み込み、ゆっくりと距離を縮める。唇と唇が触れ合う瞬間、閉じた瞼の裏で火花が散った。
マスクの下に隠していた感情が、今、解き放たれる。
きっと明日も、俺はマスクの下で名前を見つめている。だが、今この瞬間だけは――素顔のままで、彼女だけに全てを晒している。