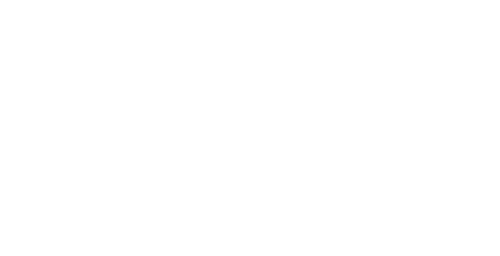授業の終わりを知らせるチャイムが、気怠い余韻を残して校舎に溶けていく。廊下には、傾き始めた太陽が投げ掛ける、どこか物憂げなオレンジ色の光が満ちていた。埃を含んでスモーキーに霞む光線が、無機質な窓ガラスに複雑な模様を描き出しては反射し、視界をぼんやりと滲ませる。国見英は、誰も居なくなった教室のドアに手を掛け、静かに閉めようとした、その時だった。
「……ねぇ、英くん。わたし、君のことを今日、少しだけ尾行してみたのだけれど」
背後の空気そのものが囁いたかのように、不意に声が降ってきた。
振り向けば、そこに苗字名前が立っている。夕陽を背負い、輪郭だけが曖昧に光っている。
「…………え?」
国見は思わず目を瞬かせた。いつものことだ、と頭の片隅では理解している。彼女の突拍子もない言動には、驚きはすれど、もはや心の底から仰天するには至らない耐性が出来てしまっている。何しろ、彼の恋人――苗字名前は、こと恋愛表現において、"常識"や"前例"といった概念を、最初から持ち合わせていないかのように振る舞うのだ。それでも、不意打ちは矢張り心臓に悪い。
「階段で擦れた、英くんの上履きの踵の音。購買で、いつもの塩キャラメルを選ぶ時の、ほんの僅かな逡巡。それから、現国の授業中、ノートの隅っこにこっそり描いていた、ちょっと不格好なペンギンの落書き。全部、ぜーんぶ、可愛かった」
にこり、と名前は天使が悪戯を思い付いた時のような、清らかでありながら、どこか蠱惑的な微笑みを浮かべる。口にしている内容は、冷静に聞けばストーカーの告白そのものなのに、不思議と国見の心に嫌悪感は湧いてこない。寧ろ、細部まで見られているという事実に、胸の奥が妙にざわつく。それは不快な種類の波紋ではなく、くすぐったさと、少しばかりの優越感が混じったような、複雑な感覚だった。
「……なんでそんな、全部憶えてんだよ。俺より、俺の行動パターン把握してる」
国見は、わざとらしく溜め息をついてみせる。だが、その吐息に苦々しさは微塵も含まれていない。寧ろ、こちらに注がれる彼女の視線が、やけに熱を帯びているように感じられて、気づけば自身の体温がじわりと上がっていくのを自覚していた。シャツの下、首筋を汗が一筋、ゆっくりと伝う感触が生々しい。
「英くん。わたし、考えていたの」
名前がふわりと首を傾げる。夕陽に透けた柔らかな髪が、揺れる度に光の粒子を弾き、きらきらと輝く。それは、静かな水面に映り込んだ夜空の星々が、ささやかに瞬いているかのようだった。
「"恋"という感情をね、もし"月の裏側"に例えるとしたら――って」
「……また、突拍子もない例え」
思わず口をついて出たが、それは否定と言うより、彼女の思考回路への半ば呆れたような感嘆に近い。
「そうかな? ほら、考えてみて。月の裏側って、わたし達が住む地球からは絶対に見ることができないでしょう? でも、確かにそこには広大な景色が存在している。まるで"不在"のように見えて、厳然と"在る"もの。誰の目にも触れない、その一番奥まった場所にこそ、一番大きくて、一番本当の気持ちが隠されているんじゃないかなって、わたしは思うの」
「……ふぅん」
国見は、名前の顔を真正面から見つめ返すことができなかった。彼女の言葉は、いつものように掴みどころがなく、詩的で、それでいて妙に核心を突いてくる。真っ直ぐに心の柔らかな部分を、的確に刺してくるような鋭さがあった。
("一番大きな気持ち"か……そんなの……)
脳裏に、先週の記憶が不意に蘇る。名前の部屋の、少しだけ沈み込むソファ。隣に座って、他愛ないゲームに興じていた筈だった。それが、ふと彼女の視線に捕らえられ、どちらからともなく手が触れ合い、指が絡み、唇が重なった。服の裾にそっと滑り込んできた彼女の指先が、微かに震えていたこと。そして、結局、最後まで――。
(……思い出すな、今は)
思考を振り払おうとする程、顔にカッと熱が集まるのがわかる。喉が妙に渇いていた。
その変化を見逃す名前ではない。くすくす、と悪戯っぽく笑う気配がした。
「英くん、今、わたしのこと、考えていたでしょう?」
「……別に。考えてない」
反射的に否定する声が、自分でも驚くほど上擦っている。
「でも、耳まで赤くなっているよ」
指摘され、ますます顔が熱くなる。
「それは……西日が眩しいから」
苦し紛れの言い訳は、我ながら稚拙だ。
「嘘。じゃあ、英くんがソファでわたしの髪を何度も撫でながら、『名前、柔らかい』って、小さな声で繰り返していたことも、全部、夢だったのかな?」
「…………名前、」
もう限界だった。これ以上、ここで彼女と会話を続けていれば、夕陽の所為だけではない赤みが、顔中に行き渡ってしまうだろう。
国見は、そっぽを向いたまま、殆ど衝動的に名前の華奢な手首を掴んだ。
「え? 英くん、どこに行くの?」
驚いたような、それでいて、どこか楽しんでいるような声が追い掛けてくる。
「……静かなとこ。お前、なんか今日、特に煩いから」
ぶっきら棒な言葉とは裏腹に、引く力は優しい。
「うん。でもね、英くんの心がそれで静かになるのなら、わたし、もっと煩くしてもいい?」
予想外の切り返しに、思わず吹き出しそうになるのを堪える。本当に、どうしてこの子は、こんなにも的確にこちらの心を揺さぶる言葉を紡ぎ出すのだろう。敵わない、と心の中で白旗を上げた。
教室を抜け出し、人気の無い階段を降りて、校舎裏の、普段は誰も寄り付かないような場所まで歩く。ひんやりとした壁に囲まれたそこは、世界から切り離されたような静寂に満ちていた。人目が無いことを確認した途端、名前は掴まれていた手をそっと解き、黙って国見の背中にぴたりと寄り添い、額を押し当ててきた。その、小さな猫が甘えるような仕草が、余りにも不意打ちで、そしてどうしようもなく愛しくて、国見は胸の奥がきゅっと締め付けられるのを感じた。
思わず、ポケットを探る。指先に、硬くて四角い感触があった。それを取り出して、名前の小さな手のひらに、そっと乗せる。
「……これ、今日、最後の一個」
包み紙に包まれた、小さなキャンディ菓子。
「あ……塩キャラメルだ」
名前が嬉しそうに声を上げる。
「うん。……半分こな。但し、噛んだら、怒るから」
我ながら、素直じゃない言い方だと思う。けれど、これが今の自分にできる、精一杯の優しい言葉だった。
「ふふ、怒らないで。でもね、英くん。わたしが先に舐めて溶けていくの、英くんは嫌じゃない?」
悪戯っぽく見上げてくる瞳が、夕陽の名残を映して煌めいている。その問い掛けに含まれた、甘やかな響きに息を呑む。
「……全然」
寧ろ、それがいい。名前が触れたものなら、なんだって。言葉にはしない想いが、短い返事に凝縮される。
息を呑むような、濃密な静寂が、二人の間にゆっくりと流れる。すぐ傍で、誰かの靴音が遠ざかっていくような気がしたが、どちらも気づかない振りをした。今は、この世界に二人きりであるかのように。
国見はもう、名前が言うところの"月の裏側"に隠してきた筈の、この大きくて厄介で、どうしようもなく愛おしい気持ちを、手放すことなどできそうにない、と確信していた。夕暮れの静寂の中、腕の中に感じる確かな温もりと、舌先で転がる小さな塩キャラメルの甘味が、その事実を静かに肯定しているようだった。