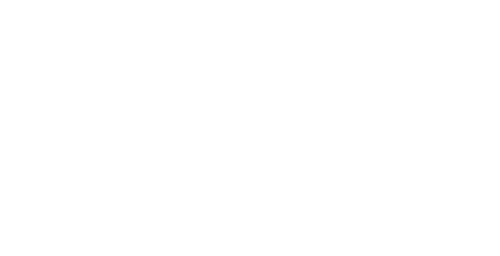北信介はマスクの下で静かに息を吐いた。
稲荷崎高校の放課後、バレー部の練習が終わった体育館には、まだ汗の匂いと熱気が微かに残っていた。体育館の外壁に沿って設置された人気のないベンチに腰を下ろした北は、疲労を感じる筋肉を解すように、ゆっくりと膝を伸ばす。制服の下に着たTシャツが湿り気を帯びて肌に張り付く感触は不快だったが、それ以上に彼の心をざわつかせる原因が別にあった。
名前。
今朝、いつものように校門で待っていた彼女の姿が鮮明に浮かぶ。朝の光に透けるような髪が柔らかく風に揺れ、深い海の底を思わせる瞳が「信くん」と呼んだ瞬間、北の胸は奇妙な痛みに締め付けられていた。
最近、名前の視線に宿る何かが、北の理性を揺るがせる。
「……参ったなぁ……」
北は額に手を当て、自嘲気味に小さく笑った。彼女との関係が変わってから、こうして一人になると否応なしに思い出す。
あの夜のこと。
初めてだった。彼女を抱いた夜。
満月の光が窓から差し込む部屋で、真っ白なシーツに横たわる名前の肌は月光を反射するように白く透き通っていた。震える指先を掴んだ、彼女の細い手の温もり。「信くん……」と掠れる声で呼ばれた瞬間、北の頭の中は真っ白になり、本能だけが彼を動かしていた。
大切にしたい。壊したくない。
でも、触れたくて仕方がない。
「……ハァ……」
もう何度目だろう。こうして、名前のことを考えるだけで心臓が張り裂けそうになる。その高鳴りは日に日に激しさを増していく。
その時、一人分の控えめな靴音が近づいてきた。
「信くん」
振り返ると、そこに彼女が立っていた。
淡いグレーのカーディガンを纏い、制服のプリーツスカートを春の風に揺らしている名前。艶やかな髪が滑らかに肩に落ち、夜の底を覗くような深い瞳が、真っ直ぐに北を見つめていた。その視線に、心臓の鼓動が急激に速くなる。
「名前……どうしたん?」
「信くんに、会いたくて」
その言葉は単純だが、名前の口から発せられると、何故か特別な重みを持った。
「……練習、終わったんでしょう?」
名前はゆっくりと近づき、北の隣に腰を下ろした。彼女の体温が、ほんの少し北の側に伝わってくる。
「……会いたいて……」
北は思わず顔を伏せた。この感情の名前を、彼はちゃんと知っている。愛情と欲望が複雑に絡み合った、制御し難い衝動。でも、名前がこんな風に素直に気持ちを口にするのは珍しく、心臓がどうしようもなく跳ね上がった。
「信くん……」
ふと、名前が手を伸ばす。北の耳に、そっと指を滑らせる触感に全身が緊張した。
「……熱いね」
「……せやろ」
名前が触れるだけで、身体中が火照ってくる。最早、抗うことは不可能だと感じていた。けれど、これ以上は――そう自制していたのに。
「信くん……マスク、取ってくれる?」
北は一瞬、動きを止めた。
「……何で?」
「……だって、顔が見たい」
名前の言葉は単純だが、その瞳に宿る感情は複雑で、北の喉の奥が乾いた。
迷いながらもマスクに指を掛けると、ふわりと彼女の指がその手を包んだ。名前の指先は冷たく、北の熱い手との温度差に、背筋に震えが走る。
「……わたしが取ってもいい?」
「……」
北は黙って頷いた。
名前はそっとマスクを引き下げる。春の風が、北の露わになった唇に触れ、僅かな痺れを感じる。名前はその唇を見つめて、静かに息を呑んだ。
「……信くんの顔、やっぱり好き」
名前の声は微かに震えていた。その声の揺らぎに、北の胸の奥で何かが弾ける。
その瞬間、背中に走った電流のような衝動に抗えなくなる。
「……名前」
北はそのまま、名前の頬を引き寄せて、唇を重ねた。
「……ん……」
名前の小さな吐息が、北の理性の糸を切り裂く。指先が彼女の髪をそっと掬い、もう片方の手は背中へ回る。
二人の呼吸が混ざり合う。名前の唇は柔らかく、思った以上に甘く、北の中の渇きを癒すようで――それでいて、もっと欲しいと思わせる。
「……っ……信くん……」
途切れる声が、北の耳を刺す。その声に、更なる熱が全身を駆け巡る。
「……好きや……」
名前の耳元で、北はそう囁いた。その言葉さえ、彼の中の熱を抑え切れない。
「……わたしも……」
名前が応える瞬間、北の胸が高鳴った。劣情に満ちた心が、自制の壁を押し崩していく。
でも――
「……今日はここまでにしとくわ」
「……え?」
名前の驚きの表情に、北は微かに笑みを浮かべた。彼は彼女の髪に口づけて、静かに目を閉じた。
「……こんなとこで、我慢できへん。もっと、ちゃんとしたいから」
北は彼女の肩をそっと抱き寄せて、耳元で囁く。名前の身体の温もりと微かな香りが、北の胸を締め付ける。
「……ほんまに。今日は、ここまで」
「……信くん……」
名前の声が切なげに震える。その声の調子に、北自身も揺らいでいることを感じる。
「……今度は、もっとちゃんとしよ」
「……うん」
名前が顔を上げると、夜の海みたいな瞳が彼を捉える。その瞳の中に映る自分の姿に、北は不思議な感覚を覚えた。
「……だから、ちゃんと好きでおってな」
北は彼女の頬をそっと撫でて微笑んだ。名前の頬の柔らかさと温かさが掌に残る。
「当たり前」
名前のその答えは驚く程に力強かった。
次に触れる時は、もっと深く、もっと強く。そんな予感に、北はそっと笑った。二人の間に流れる空気は約束で満ちていた。
――きっと、彼女の全てを知るには、まだ時間が必要だ。
でも、この熱が冷めることはない。
だから、もう少しだけ。焦らずに、名前の全てに触れたい。
春の空気が二人を包む中、北信介は静かな誓いを胸に刻んだ。