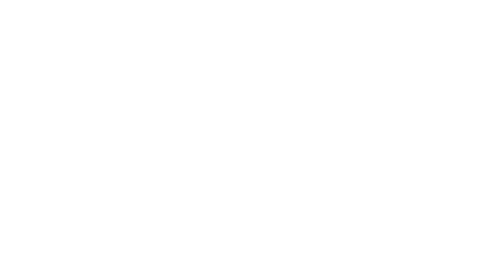あの日から、わたしの世界は"飛雄くん"で回っている。
見つめる、見つめる、ただ、見つめる――
自販機の無機質な光が、吐く息の白さをぼんやりと照らしている。指先が悴むような冷気の中、俺は無意識にピースサインを作って、『あったか~い』の列にあるボタンを狙った。今日の練習はマジで骨身に沁みた。部室から一歩外に出た途端、この冷え切った空気が喉の奥をキン、と鋭く刺してくる。もう冬がそこまで来ている証拠だ。腹の底から『ポークカレー温玉載せ』を欲するくらいには、全身がエネルギーを渇望している。
……それにしても、だ。なんで、アイツはあんな見るからに怪しい格好で、こんな場所に突っ立ってるんだ?
俺は自販機に寄り掛かる振りをしながら、さっきから視界の端でチラつく人影に意識を向けた。――間違いねぇ、あれは名前だ。くすんだサンドベージュのコート。フードをすっぽり目深に被って、顔の殆どを隠してるつもりらしい。だが、無駄だ。俺にはすぐにわかる。俯き加減の首の角度、寒そうに前で組まれた指先、そして、時折夜風に悪戯されて揺れる、フードの隙間から覗く数本の髪。
あんな取って付けたような変装、バレバレなんだよ。
つーか、こっちを穴が開くんじゃないかってくらいガン見してるのも、とっくに気づいてる。外灯の影とか、意味不明な植え込みの裏とか、あからさまに物陰を選んで隠れてるつもりなんだろうが、その存在感はガラスみたいに透けてる。物理的な意味じゃねぇ。気配が、だ。だって、俺の意識が、視界の端が、アイツの存在を示す妙なノイズでざわざわと曇ってるんだから。こうやって、姿が見えなくても、遠くからでも視線を感じると、どうしようもなく胸の奥が落ち着かなくなる。
しかも、手には何やらメモ帳とペンまで握り締めてやがる。
……またアレか。例の、意味不明な尾行メモ。
以前、半ば無理やり見せられた『飛雄くんの好きな飲み物リスト(季節変動あり)』とか、『今日のスパイクの角度と決定率の相関に関する考察』とか、一体、誰が得するのか全く理解不能な研究資料。でも、正直に言うと……いや、絶対に本人には言わねぇけど、あれ、見せられるとめちゃくちゃ嬉しい自分が居る。だって、それはアイツが四六時中、俺のことだけを見て、考えてたっていう、紛れもない証拠だから。
それに、アイツは――
フードで顔を隠そうが何をしようが、そういう表面的なものじゃなくて、その奥にある感情が、俺には何故か透けて見えるんだ。いつもは静かで、底が見えないくらい冷たく見える瞳の奥に、時折、熾火みたいに赤い熱がポッと灯る瞬間がある。口では素っ気ないことしか言わない癖に、俺のことを見てる時だけ、ほんの少し呼吸が浅くなってることに気づいてる。
「……あんなんで隠せてると思ってんのかよ……」
思わず独り言が漏れた。俺は買ったばかりの二つの缶飲料の温かさを確かめるように握り締め、自販機の脇に設置された、冷え切ったプラスチックのベンチにどすんと腰を下ろす。フードの彼女は、まだ物陰から微動だにせず、じぃっとこっちを観察し続けている。その執念深さと言うか、マイペースさと言うか……。
……ああ、もう、いい加減、こっちがもたねぇ。呼ぶか。
「おい、名前。見えてんぞ」
俺がぶっきら棒に声を掛けると、途端、彼女の肩が大袈裟なくらいビクンと揺れた。フードの暗がりから、双眸がきらりとこちらを捉える。吸い込まれそうな、深海みたいな色。その瞳が今、はっきりと俺だけを映している。
名前はフードを被ったまま、まるで音を立てない猫のような、それでいて妙に堂々とした足取りで、ゆっくりとこちらに近づいてきた。
「……隠れていたつもりだったのに」
フードの中から、吐息みたいにふんわりとした声が聞こえる。なのに言ってる内容は、本気で完璧な隠密行動が成功していると信じていた感満載で、俺は思わず吹き出しそうになるのを堪えた。
「無理だろ。顔、全部出てた」
「嘘。ちゃんと深く被ったよ。鏡で確認した」
「……深くても、目が笑ってた。後、ずっとこっち見てた」
「……そう」
名前がそこで、ふ、と小さく息だけで笑った気配がした。
多分、俺が気づくことなんて、最初からわかってたんだ。それでもやりたかったんだろう。"わたしを見つけてくれる"という、子供みたいな、少し拗ねたようなわがままを、あの静かなフードの中でこっそりと抱えながら。そういうところが、本当に面倒臭いけど、放っておけない。
「それにしても……さっきから何してたんだよ、あんな所で?」
俺が改めて訊くと、彼女は少しだけ間を置いてから、事もなげに答えた。
「飛雄くんが、自販機の前でどのボタンを何秒で見つけて、何秒で押すのか、その思考プロセスと所要時間を計測していたの」
「……はあ? なんの意味があんだよ、それ」
呆れて声が出た。
「好きな人を観察するのは、わたしのライフワークであり、趣味だよ」
完全に悪びれる様子ゼロ。それどころか、フードの奥から覗く真っ直ぐな瞳でそう断言されて、俺は顔にカーッと熱が集まるのを感じた。こいつのこういうところが……!
「……や、やめろ、そういう恥ずかしいこと言うの……っ」
「どうして? さっき、嬉しいって顔に書いてあったけれど」
「う、うるせぇ! 書いてねぇ! 言われると……その、顔が……熱くなるだろうが!」
しどろもどろになる俺を見て、名前が今度はハッキリと、くすくすと喉を鳴らして笑った。
「だから、飛雄くんもフードを被っているの? 照れているのを隠す為に」
「違う! これはだな、ただの風邪対策だ!」
咄嗟に、俺もフードを深く被り直す。
「……ふぅん? それにしては、耳まで真っ赤になっているけれど?」
……ダメだ、こいつには敵わねぇ。
完全に心の中まで見透かされてる。フードなんて、何の意味も成さねぇ。
それは俺だけじゃなくて、名前の方も同じだ。この、計算なのか天然なのか判別不能な、あざとくないのに強烈な可愛さに、俺は毎日、為す術もなく撃沈させられてる。
「……もう知らねぇ……勝手にしろ……」
そう吐き捨てるように言って、俺は彼女が座るスペースを空けるように、ベンチの端にずずっと寄る。そして、さっき買ったばかりの、まだ熱い缶ココアを、無言で名前の手に押し付けた。
「……ありがとう」
名前は小さく笑ってそれを受け取る。その瞬間、冷えた彼女の指先が、俺の手に触れた。ただそれだけなのに、心臓が馬鹿みたいに跳ね上がる。やべぇ、このドキドキしてる感じ、絶対バレてる。そう思うと余計に意識してしまって、俺はますますフードを深く被り直した。
でも、やっぱりそんな抵抗は無意味だった。
だってその直後、名前が俺の耳元に顔を寄せ、マフラーの隙間から、悪戯っぽい熱を含んだ声で囁いたんだ。
「ねぇ、飛雄くん。今度はそのフードの中も、じっくり観察していい?」
その破壊力抜群の言葉に、俺は耐え切れず、
「ボゲェ!!!」
と、自分でも驚くようなデカい声で叫んで、口に含み掛けていた自分の分の缶飲料(コーンスープ)を思いっ切り前方に吹いた。
――ああ、くそっ。やっぱりこいつには、一生敵わねぇ。