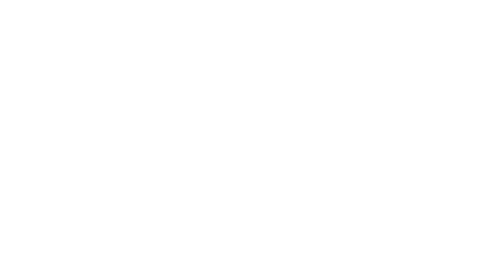影山飛雄にとって、『飛ぶ』とは極めて現実的な行為だった。
床を蹴る力、空中で体勢を制御する筋力、そしてボールを最も正確な位置へと送り届ける為の精密な計算。それは、反復練習と揺るぎない意志によってのみ獲得できる、具体的な技術の総称だ。コートという限定された空間で、重力に逆らい、勝利へと繋げる為の跳躍。そこに夢想の入り込む余地など、彼の中には微塵も存在しなかった。理論と実践、汗と経験。それら物理的な要素の積み重ねこそが、彼にとっての『飛ぶ』ことの全てだった筈だ。
けれど、今――影山は、自分がこれまで知ることのなかった、全く異なる質の『飛ぶ』感覚の入り口に立っていることを、漠然と、しかし確実に感じ始めていた。その感覚を齎すのは、他の誰でもない、名前という存在だった。
初めて二人きりの夜を迎えた時のことを、影山は今でも鮮明に憶えている。
部屋の薄明かりが、彼女の輪郭を柔らかく縁取っていた。慣れない空間、すぐ隣にある温もり。どう動けばいいのか、何を話せばいいのか、まるで分からなかった。バレーボールを手にしている時のような、絶対的な自信はどこにもない。指先は冷え、動きはロボットのようにぎこちなかった。それまで、人生の全てをバレーボールに捧げてきた。恋愛経験など、当然のように皆無。未知の領域に対する戸惑いが、全身を強張らせていた。
そんな影山を見て、名前は静かに微笑んだ。「怖い?」と、澄んだ声で問い掛けてきた。
その声は、凪いだ水面のように穏やかで、影山の張り詰めた神経を僅かに緩めた。
怖いわけがない。そう即答しようとして、しかし言葉が喉の奥でつかえた。違う。これは恐怖ではない。もっと別の、名付けようのない感情だ。コート上で感じるプレッシャーとも違う。
「名前に、嫌われたくねぇ」
ぽつりと零れたのは、自分でも驚くほど弱々しく、不格好な本音だった。セッターとして仲間を信頼する気持ちとは全く異なる、もっと個人的で、脆くて、どうしようもなく切実な感情。こんな情けないことを口にするつもりはなかったのに、と影山は内心で舌打ちした。
けれど、名前は驚きも、ましてや呆れも見せず、ただ穏やかに微笑みを深めただけだった。そして、そっと影山の強張った頬に手を添えた。ひんやりとした指先が、熱を持った肌に心地よかった。まるで、道に迷った幼子を安心させるように、その眼差しはどこまでも優しかった。
「わたしも、飛雄くんに嫌われたくないよ」
その一言が、魔法のように、影山の中で固く絡まっていた何かを、するりと解きほぐしていった。張り詰めていた糸が切れ、安堵と共に、ふっと身体の力が抜けるのを感じた。
あれから、数ヶ月の季節が巡った。
影山は、日常のふとした瞬間に、再びあの『飛ぶ』ような感覚を覚えるようになっていた。
それは、試合で最高のトスが決まった時のような、アドレナリンが沸騰する昂揚とは明らかに異質なものだった。もっと静かで、個人的で、そして甘美な感覚。
例えば、授業中、窓の外を眺めていた名前が、不意に横髪を耳に掛けた、その何気ない仕草を目にした時。
例えば、放課後の図書室の隅で、彼女が静かに本の世界に没頭している横顔を見つけた時。
例えば、帰り道、何の気なしに繋いだ名前の手のひらの、温かさと柔らかさを感じた時。
その度に、影山の胸の内側で、何かがふわりと浮き上がるような感覚に襲われるのだ。地に足は着いている筈なのに、身体が内側から軽くなっていくような、奇妙な浮遊感。重力から解き放たれるような、不思議な心地よさ。
――これは、名前という存在そのものが、俺を飛ばせているのだろうか。コートの外で、俺は違う飛び方を知り始めているのだろうか。
「……なぁ」
或る日の午後、名前の家のリビング。ソファに深く腰掛けた影山は、膝の上で微睡んでいる彼女に向かって、ぼそりと口を開いた。彼女の体重は心地よい重みとなって伝わり、その温もりが影山を安心させていた。名前は影山の胸に頬を預け、穏やかに目を閉じている。部屋には、午後の柔らかな日差しと、彼女の纏うシャンプーの清潔な香りが満ちていた。
「ん?」
眠たげな、甘い声が返ってくる。
「俺は、バレーでなら、まあ、飛べるけど……それ以外じゃ、全然、まだまだだよな」
唐突で、脈絡のない問い掛けだった。自分でも、何故そんなことを口にしたのかよく分からない。ただ、最近感じるこの不思議な感覚について、彼女に確かめてみたかったのかもしれない。
しかし、名前は眉一つ動かさなかった。それどころか、微かに唇に笑みを浮かべ、影山の着ているTシャツの裾を、細い指先でくるくると弄び始めた。
「飛雄くんは、ちゃんと飛んでいるよ。わたしには見える」
「……そうか?」
自分では全く実感がない。寧ろ、地に足が着いていないような頼りなさを感じるくらいだ。
「うん。例えそれが、まだ骨組みだけの、不格好な羽だったとしても。飛ぼうとする強い意志があれば、ちゃんと空を掴めるんだよ」
「??? ……難しいこと、言うな。よく分かんねぇ」
影山が正直に困惑を口にすると、名前はくすりと喉を鳴らして笑った。その振動が、胸を通して心地よく伝わってくる。
「飛雄くんが、わたしと一緒に居る時の顔、知ってる?」
「……知るか。どんな顔してんだよ、俺」
「それは、秘密」
悪戯っぽく笑いながら、名前はゆっくりと身を起こした。そして、影山の顎にそっと手を添え、吸い寄せられるように顔を近づけてくる。影山は息を呑んだ。
彼女の唇が、自分のそれに、そっと触れた。
その瞬間、影山の思考は完全に停止した。世界から音が消え、色彩が失われ、ただ唇に触れる柔らかな感触と、すぐ間近にある名前の気配だけが、絶対的な現実として存在していた。心臓が、肋骨の内側で狂ったように跳ね回り、その音が頭の中にまで響くようだった。
唇が離れても、影山は暫く動けなかった。
「あのね、飛雄くん」
名前の囁きが、熱くなった耳朶を優しく撫でる。
「……な、なんだよ」
漸く絞り出した声は、掠れていた。
「飛雄くんはね、もうとっくに、わたしと一緒に飛んでいるんだよ。この、広い空を」
その言葉が、すとんと影山の胸の奥に落ちた。
ゆっくりと息を吐き出す。肺を満たす空気が、いつもより甘く感じられた。
この、胸を満たす温かな浮遊感。地に足が着かないような、頼りなくも心地よいこの感覚に、もし名前を付けるとしたら――。
「好きだ」
それ以外に、言葉が見つからなかった。
声に出した途端、その感情がより一層、確かなものとして身体中に広がっていくのを感じる。
影山は無言のまま、目の前の名前を強く抱き締めた。壊れ物を扱うような、それでいて決して離さないという意志を込めて。まるで、自分の中に芽生え始めたばかりの、不確かな翼の羽ばたきを確かめるかのように。
――骨組みだけの羽でも。
彼女の言葉が、再び頭の中で響く。
意味はまだ、完全には理解できないかもしれない。けれど、それでいいと思えた。
この腕の中に名前が居る。それだけで、どんなコートよりも広く、どこまでも高い空が広がっているような気がした。
二人ならば、きっと、どこへでも飛んでいける。
そんな確信にも似た予感が、影山の心を静かに満たしていくのだった。