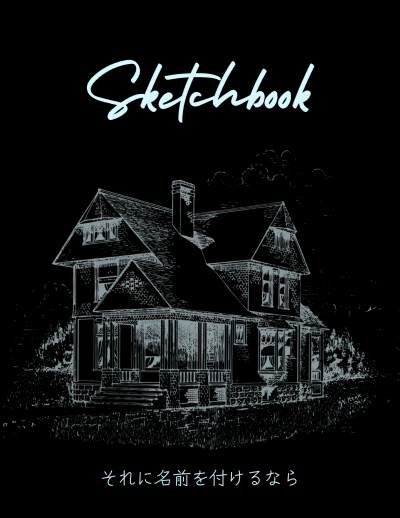
-スケッチブックの告白-
しとしと、と窓硝子を叩く雨音は、世界から余分な音を洗い流してくれる優しいノイズだ。湿ったアスファルトの匂いが、古書の黴と、焙煎された珈琲豆の香りと混じり合い、『雨滴文庫』の空気を唯一無二のものに仕立て上げている。雨の日にだけ、祖父が道楽で開くこのブックカフェは、私の人生の全てだった。少なくとも、あの喧しい程に生命力で満ち溢れた彼と出逢うまでは。
カウンター席の隅、特等席で、膝に置いていたスケッチブックを捲る。鉛筆で描かれた、線の集合体。そこに居るのは、いつだって同じ男の子だった。ボールを打つ瞬間のしなやかな背中。眉間に皺を寄せ、コートの向こうを睨み付ける鋭い眼差し。仲間からの声援に、一瞬だけ見せる子供っぽい笑顔。
五色工くん。
私の恋人。
事実を反芻する度、心臓が熟れ過ぎた果実のように甘く疼く。私達は、もう子供ではない一線を越えた。工くんの熱も、荒い息遣いも、私を求める声も、全て知っている。それなのに、だ。頁を繰る指先が、彼の横顔をなぞったラインの上で躊躇う。身体の距離はゼロになったと云うのに、心の距離は未だに測り兼ねていた。遠い星の光が何光年も掛けて地球へ届くように、私の本当の気持ちが、彼へ届くまでには、途方もない時間を費やしてしまう気がする。
この感情は一体、何なのだろう。
"好き"と云う言葉は余りに単純で、複雑な心の機微を表現するには陳腐過ぎる。工くんがバレーボールに向ける、燃え盛るような情熱。その輝きに焦がれる一方で、彼の世界の中心は、あのカラフルなボールとネットなのだと突き付けられる、ちくりとした寂しさ。彼の隣に居る資格が、自分にあるのかと云う心許なさ。そして、そんな感傷的な自身への、僅かな嫌悪。
もし、ぐちゃぐちゃと絡まった感情の毛糸玉に名前を付けるなら。
私は答えを見つけられないまま、そっとスケッチブックを閉じた。
ドタンッ!
店の古いドアが、壊れんばかりの勢いで開かれた。音だけで、誰が来たのかは明白だった。
「名前! 居る!?」
「……工くん、ドアが悲鳴を上げているよ」
息を切らし、髪から雨の雫を滴らせながら立っていたのは、案の定、五色工その人だった。白鳥沢学園のジャージはしっとりと濡れ、彼の体温で湯気が立ち昇っているように見える。寮暮らしの彼が、部活帰りに態々遠回りして、降雨の中を走ってきたのだと思えば、胸の奥がきゅう、と鳴った。
「わ、悪い! でも、どうしても顔が見たくなって……」
そう言って、大型犬のように素直な瞳で見つめるものだから、敵わない。私は棚から乾いたタオルを手に取り、工くんの元へ駆け寄った。
「風邪を引くよ。ほら、動かないで」
背伸びをして、工くんの濡れた黒髪をわしわしと拭く。ぱっつんの前髪の下で、凛々しい眉が気持ち良さそうに下がった。制汗剤の芳香と、雨と、汗の匂い。彼の放つ生々しいまでの生命力に、くらりとする。
「ありがとう、名前。助かる」
「うん。……練習、どうだった?」
「ああ! 今日も、牛島さんとロードワークで張り合ってきた! 後少しで勝てたんだけど……! それに、クロスも前より鋭くなった気がする! 監督にも、まあまあだな、って言われたしな!」
得意気に胸を張る姿は、自信に満ち溢れていて眩しい。けれど、声の張りに反して、瞳の奥にほんの僅かな翳りが過ったのを見逃さなかった。工くんは時々、強気な発言の鎧で、自分の弱さを隠そうとする。本当は、何か壁にぶつかっているのだろう。もっと鋭いクロスを打ちたい、と云う彼の最近の悩みを、私は知っている。
でも、指摘はしない。工くんのプライドを、私が踏み荒らすわけにはいかないから。私は只、彼の言葉を信じる振りをして、微笑むだけ。
「そう。工くんは凄いね」
「だろ! 俺は白鳥沢の次期エースだからな!」
煽てられ、途端にご機嫌になるのが彼らしい。そんな単純さが愛おしくて、同時に、少しだけ哀しい。私が触れられない、工くんの聖域。その境界線で、私はいつも立ち尽くしている。
祖父直伝のココアを二人で飲みながら、他愛もない話をした。クラスのこと、美術部の課題のこと、五色家で飼っている犬の話。穏やかな時間が流れる。でも、私の心の隅には、名付けられない感情が澱のように溜まっていた。
工くんがコートで見せる、鬼気迫る表情。それは、私の前では決して見せない顔。
工くんがバレーボールに捧げる、人生の全て。それは、私が決して立ち入れない世界。
この気持ちはもしかしたら、恋ではないのかもしれない。憧れと、嫉妬と、庇護欲と、幾等かの諦めが混ざり合った、名前のない何か。
「……それに名前を付けるなら」
ぽつりと、無意識に言葉が漏れた。
「ん? 何か言った?」
工くんがきょとんとした顔で、私を見る。慌てて、首を横に振った。
「ううん、何でもない。ココア、美味しいねって」
嘘を吐いた罪悪感で、胸がちりりと痛んだ。
 名前が淹れてくれたココアは、甘くて優しい味がした。練習でささくれ立った神経が、温かさでゆっくりと解きほぐされていくのを感じる。目の前で、大きなカップを両手で包むように持ち、こくりと小さく嚥下する名前の姿は、まるで一枚の絵画みたいだった。ふわりと柔らかそうな髪、長い睫、ほんのりと上気した白い頬。
この子が、俺の彼女なんだ。
その事実を噛み締める度に、胸がはち切れそうな程に満たされる。初体験を済ませてから、想いは一層強くなった。彼女の全てを知ってしまった、と云う全能感と、だからこそ、俺が絶対に守らなければいけない、と云う強烈な責任感。名前に触れたい、もっと深く繋がりたい、と云う衝動が、常に腹の底で燻っている。
だが、同時に戸惑いもあった。どう接するのが正解なのか、分からない時があるのだ。
今日の練習も、結局、最後まで納得の行くクロスは打てなかった。鷲匠監督からは檄を飛ばされ、白布さんには「一年坊主が調子に乗ってんじゃねえ」と嫌味を言われる始末。悔しくて、情けなくて、本当は今直ぐにでも、名前に抱き付いて、弱音を吐いてしまいたかった。
でも、できなかった。
彼女の前では、格好良い"次期エースの五色工"で在りたい。弱くて、未熟な自分なんて、見せたくない。だから、つい虚勢を張ってしまう。名前が「凄いね」と微笑む度、純粋な瞳に嘘を吐いているようで、胸が痛んだ。
「ちょっと、新しいブレンドの試飲をしてくるね」
名前がそう言って、カウンターの奥に居る、お祖父さんの元へ向かった。一人残された俺は、手持ち無沙汰にテーブルの上を見回す。そこに、彼女がよく抱えているスケッチブックが、無造作に置かれているのが目に入った。
見てはいけない。そう、頭では理解していた。プライベートなものだ。だけど、名前が何を描いているのか、ほんの少しだけ、と云う好奇心が勝ってしまった。罪悪感と共に、こっそりとページを覗き込む。
息を呑んだ。
そこに居たのは、俺だった。
汗を迸らせて、スパイクを打つ俺。タイムアウト中、タオルで頭を覆って俯く俺。サービスエースを決めて、仲間とハイタッチを交わす俺。牛島さんを睨み付ける、悔しさに満ちた俺。
それは、俺自身ですら意識してない、剥き出しの瞬間ばかりだった。ページを捲る指が震える。どの絵にも、愛情と、祈るような敬意が込められていると、素人の俺にも、痛い程に伝わった。
そして、一枚のスケッチの隅に、名前の小さな文字が添えられているのを見つけてしまった。
『悔しい顔もカッコイイと思うのは、私だけかな』
――ドクン、と心臓が大きく跳ねた。
何だ、これ。
名前は見ていたのか。俺の、こんな格好悪いところまで。全部。
俺が必死に隠そうとしていた弱さも、未熟さも、全部を知った上で、それでも、俺を――。
「お待たせ。お祖父ちゃんが、新作の『黄昏時の片想いクッキー』を焼いたんだって」
名前が戻ってくる。俺はスケッチブックから、視線を上げることができない。どんな顔をすればいいのか、分からなかった。
「工くん……?」
怪訝そうな声音。俺は意を決して、画帖を指差した。声が震えた。
「……これ、全部、俺なんだな」
名前の頬が、熟れた林檎の如く真っ赤に染まった。彼女は慌てて、スケッチブックを閉じようとするが、俺はそれを手で制した。
「見せてくれ」
真っ直ぐに、彼女の双眸を見つめる。名前は怯えたように視線を彷徨わせた後、観念した様子で小さく頷いた。
俺は一枚一枚、ゆっくりとページを捲った。名前がどんな想いで、俺を見ていたのか、線の一本ずつから伝わるようだった。俺はとんでもなく勘違いをしていたのかもしれない。格好付ける必要なんて、どこにもなかったんだ。名前は、強い俺も、弱い俺も、全部をひっくるめ、受け止めてくれていた。
最後の紙面を捲り終え、俺はスケッチブックを閉じた。そして、眼前で俯いている名前の手を、両手で確りと包み込んだ。
「名前」
名前を呼ぶと、彼女の肩がぴくりと震えた。
「俺、ずっと、名前に格好悪いところ、見せたくなかった。でも、違ったんだな」
「……」
「好き、とか、そう云う簡単な言葉じゃ、もう足りない。俺が、名前に感じてるこの気持ちに、まだ名前は付けられない。独り占めしたいし、守りたいし、でも、名前の前では、一番強く在りたいし……ぐちゃぐちゃで、自分でもよく分からない。でも、」
一度、言葉を切り、彼女の顔を覗き込む。潤んだ諸目と視線が絡んだ。
「名前が、俺をこんな風に見てくれてるって、分かったから……俺、この気持ちをもっとデカくして、いつか、世界で一番格好良い名前を付けてやるから。だから……待っててくれ」
名前の瞳から、ぽろ、と大粒の涙が零れ落ちた。
「私……私も、工くんへの気持ちに、名前を付けられずにいたの。好き、だけじゃ、足りなくて……でも、どう言えばいいのか、分からなくて……」
嗚咽混じりの声が、愛おしくて堪らない。
「それでいいんだよ。これから、二人で探していけばいい」
「……うん」
握った手に力を込める。雨音だけが響く静かな店内で、俺達の間に在った見えない壁が、音を立てて崩れるのが分かった。
そうだ。焦る必要なんてない。この、胸を焦がすようでいて、心の底から安らげる、不思議な感情。今はまだ、名前なんてなくていい。
俺はいつもの調子を取り戻し、ニッと笑ってみせた。
「ま、取り敢えず、今の感じに、仮の名前を付けるなら……」
名前が涙に濡れた眼差しで、俺を見上げる。
「"世界で一番幸せな男"……だな!」
俺がそう言うと、名前は一瞬きょとんとした後、ふわりと花が咲くように笑った。その笑顔が見られただけで、もう、どんな名前だっていい気がした。
名前が淹れてくれたココアは、甘くて優しい味がした。練習でささくれ立った神経が、温かさでゆっくりと解きほぐされていくのを感じる。目の前で、大きなカップを両手で包むように持ち、こくりと小さく嚥下する名前の姿は、まるで一枚の絵画みたいだった。ふわりと柔らかそうな髪、長い睫、ほんのりと上気した白い頬。
この子が、俺の彼女なんだ。
その事実を噛み締める度に、胸がはち切れそうな程に満たされる。初体験を済ませてから、想いは一層強くなった。彼女の全てを知ってしまった、と云う全能感と、だからこそ、俺が絶対に守らなければいけない、と云う強烈な責任感。名前に触れたい、もっと深く繋がりたい、と云う衝動が、常に腹の底で燻っている。
だが、同時に戸惑いもあった。どう接するのが正解なのか、分からない時があるのだ。
今日の練習も、結局、最後まで納得の行くクロスは打てなかった。鷲匠監督からは檄を飛ばされ、白布さんには「一年坊主が調子に乗ってんじゃねえ」と嫌味を言われる始末。悔しくて、情けなくて、本当は今直ぐにでも、名前に抱き付いて、弱音を吐いてしまいたかった。
でも、できなかった。
彼女の前では、格好良い"次期エースの五色工"で在りたい。弱くて、未熟な自分なんて、見せたくない。だから、つい虚勢を張ってしまう。名前が「凄いね」と微笑む度、純粋な瞳に嘘を吐いているようで、胸が痛んだ。
「ちょっと、新しいブレンドの試飲をしてくるね」
名前がそう言って、カウンターの奥に居る、お祖父さんの元へ向かった。一人残された俺は、手持ち無沙汰にテーブルの上を見回す。そこに、彼女がよく抱えているスケッチブックが、無造作に置かれているのが目に入った。
見てはいけない。そう、頭では理解していた。プライベートなものだ。だけど、名前が何を描いているのか、ほんの少しだけ、と云う好奇心が勝ってしまった。罪悪感と共に、こっそりとページを覗き込む。
息を呑んだ。
そこに居たのは、俺だった。
汗を迸らせて、スパイクを打つ俺。タイムアウト中、タオルで頭を覆って俯く俺。サービスエースを決めて、仲間とハイタッチを交わす俺。牛島さんを睨み付ける、悔しさに満ちた俺。
それは、俺自身ですら意識してない、剥き出しの瞬間ばかりだった。ページを捲る指が震える。どの絵にも、愛情と、祈るような敬意が込められていると、素人の俺にも、痛い程に伝わった。
そして、一枚のスケッチの隅に、名前の小さな文字が添えられているのを見つけてしまった。
『悔しい顔もカッコイイと思うのは、私だけかな』
――ドクン、と心臓が大きく跳ねた。
何だ、これ。
名前は見ていたのか。俺の、こんな格好悪いところまで。全部。
俺が必死に隠そうとしていた弱さも、未熟さも、全部を知った上で、それでも、俺を――。
「お待たせ。お祖父ちゃんが、新作の『黄昏時の片想いクッキー』を焼いたんだって」
名前が戻ってくる。俺はスケッチブックから、視線を上げることができない。どんな顔をすればいいのか、分からなかった。
「工くん……?」
怪訝そうな声音。俺は意を決して、画帖を指差した。声が震えた。
「……これ、全部、俺なんだな」
名前の頬が、熟れた林檎の如く真っ赤に染まった。彼女は慌てて、スケッチブックを閉じようとするが、俺はそれを手で制した。
「見せてくれ」
真っ直ぐに、彼女の双眸を見つめる。名前は怯えたように視線を彷徨わせた後、観念した様子で小さく頷いた。
俺は一枚一枚、ゆっくりとページを捲った。名前がどんな想いで、俺を見ていたのか、線の一本ずつから伝わるようだった。俺はとんでもなく勘違いをしていたのかもしれない。格好付ける必要なんて、どこにもなかったんだ。名前は、強い俺も、弱い俺も、全部をひっくるめ、受け止めてくれていた。
最後の紙面を捲り終え、俺はスケッチブックを閉じた。そして、眼前で俯いている名前の手を、両手で確りと包み込んだ。
「名前」
名前を呼ぶと、彼女の肩がぴくりと震えた。
「俺、ずっと、名前に格好悪いところ、見せたくなかった。でも、違ったんだな」
「……」
「好き、とか、そう云う簡単な言葉じゃ、もう足りない。俺が、名前に感じてるこの気持ちに、まだ名前は付けられない。独り占めしたいし、守りたいし、でも、名前の前では、一番強く在りたいし……ぐちゃぐちゃで、自分でもよく分からない。でも、」
一度、言葉を切り、彼女の顔を覗き込む。潤んだ諸目と視線が絡んだ。
「名前が、俺をこんな風に見てくれてるって、分かったから……俺、この気持ちをもっとデカくして、いつか、世界で一番格好良い名前を付けてやるから。だから……待っててくれ」
名前の瞳から、ぽろ、と大粒の涙が零れ落ちた。
「私……私も、工くんへの気持ちに、名前を付けられずにいたの。好き、だけじゃ、足りなくて……でも、どう言えばいいのか、分からなくて……」
嗚咽混じりの声が、愛おしくて堪らない。
「それでいいんだよ。これから、二人で探していけばいい」
「……うん」
握った手に力を込める。雨音だけが響く静かな店内で、俺達の間に在った見えない壁が、音を立てて崩れるのが分かった。
そうだ。焦る必要なんてない。この、胸を焦がすようでいて、心の底から安らげる、不思議な感情。今はまだ、名前なんてなくていい。
俺はいつもの調子を取り戻し、ニッと笑ってみせた。
「ま、取り敢えず、今の感じに、仮の名前を付けるなら……」
名前が涙に濡れた眼差しで、俺を見上げる。
「"世界で一番幸せな男"……だな!」
俺がそう言うと、名前は一瞬きょとんとした後、ふわりと花が咲くように笑った。その笑顔が見られただけで、もう、どんな名前だっていい気がした。

