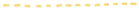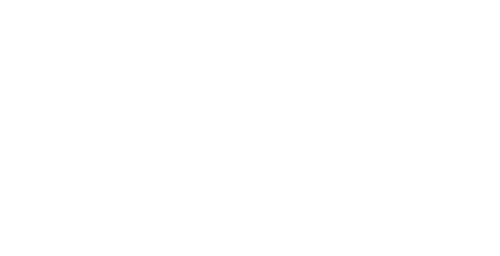届かない夢の中で泣いていた君を、現実の中で守ると誓った。
夢の中で、名前が泣いていた。
それは声もなく、ただ静かに涙を零すような、そんな哀しい泣き顔だった。俺の目の前で華奢な肩を震わせ、白い顔を伏せている。その姿が打ち捨てられたアンティークドールのようで、胸が締め付けられた。
「名前」
呼び掛けても、その声は霧散するように届かない。手を伸ばしても、指先は虚しく空を掻くだけで、彼女の柔らかな肌に触れることすら叶わない。厚いガラス板一枚を隔てたように、俺達の間には絶対的な断絶が存在していた。
俺の声は深淵へと続く井戸に投げ込まれた小石のように、音もなく吸い込まれていく。そして、気づけば彼女の姿も、その涙の理由も、全てが底なしの闇の中へと溶けて消えていった。
目が覚めた時、喉が砂漠を彷徨った後のように、カラカラに渇き切っていた。心臓だけが鳥籠の中で暴れる鳥のように、胸の奥で不自然な程に激しく、大きく脈打っている。窓から差し込む朝の光は、いつもよりどこか希薄で、薄絹を一枚隔てたように柔らかく、そして肌を刺すように冷たかった。
……ただの夢だ。そう自分に言い聞かせるのに、それ程の時間は掛からなかった。俺はどちらかと言えば、現実的な思考をする人間だ。根拠のない不安に振り回されるのは、正直、性に合わない。バレーの試合中、0.5秒の間に思考を巡らせるように、この悪夢も分析し、処理できる筈だった。
けれど――心の奥底に微かな棘が刺さったような、そんな不快な感覚が消えずに残っていた。
「京治くん」
教室の窓辺、朝の喧騒がまだ遠いその場所で声を掛けられた瞬間、俺はあの忌まわしい夢の残滓を鮮明に思い出していた。心臓が、またあの時のように嫌な音を立て始める。
振り向いた先には、いつもと変わらない名前が居た。
陽光を浴びて煌めく髪は上質な絹糸のよう。その下に覗く白い肌は血の気がない程に透き通っていて、触れれば溶けてしまいそうな儚さを纏っている。夜の海を思わせる深い色の瞳は、どこか感情の機微を読み取らせない不思議な光を宿していた。繊細で、けれど揺るぎない輪郭を持つその美しさは、精巧に作られたビスクドールのようだ。
「おはよう。……珍しいね、こんなに早く来ているなんて。寝坊はしなかったみたいだ」
努めて平静を装い、冗談めかして言うと、名前は形の良い眉をほんの少しだけ寄せ、それからふわりと薄氷が解けるように微笑んだ。その笑顔はいつだって、俺の心を捕らえて離さないが、同時にどこか危うさを孕んでいることを、俺は知っていた。彼女の笑顔は、必ずしも心の底からの安心の証じゃない。
「わたし、京治くんを待っていたの」
その透明感のある、けれど芯のある声が鼓膜を揺らす。
「……教室で?」
「ううん。夢の中で」
一瞬、全身の血の気が引くのを感じた。指先が急速に冷えていく。あの夢の中で、俺が彼女に届かなかったように、名前もまた、俺に何かを伝えようとしていたのだろうか。
「……名前も、夢を見たの?」
辛うじて絞り出した声は、自分でも驚く程に掠れていた。
「そうだよ。ちょっと怖い夢。……でも、宝石箱に仕舞っておいたから、もう大丈夫」
宝石箱――。
その言葉の選び方が余りにも彼女らしくて、胸の奥に刺さった棘が、更に深く食い込むような鈍い痛みを感じた。名前は時折、こうして常人には理解し難い、独自の感性で世界を切り取る。それが彼女の魅力であり、同時に、俺を不安にさせる要因でもあった。
俺はそれ以上、夢の内容について詳しく訊くことができなかった。彼女が「大丈夫」と言うのなら、それを信じるしかない。けれど、ずっと心の片隅で燻っていた。彼女がその「怖い夢」をたった一人で、あの小さな微笑みの下に仕舞い込んでしまうことが。まるで、誰にも見せてはいけない秘密のように。
抱き締めて、その温もりを確かめるわけでも、安心させるような甘い言葉を重ねるわけでもない。ただ、その日は一日中、意識的に彼女を見ていた。少しでも目を離したら、夢の中のように消えてしまいそうで。
昼休み、中庭のいつものベンチで、名前が手作りの弁当を静かに口に運んでいる時も。――その細い指が箸を操る様は、精密な機械のようだった。
授業中、窓の外をぼんやりと見つめている、彼女の美しい横顔も。その瞳は何を映し、何を思っているのだろうか。時折、風に揺れる柔らかな髪が、その白い頬を掠める様が余りにも儚げで、触れた瞬間に壊れてしまいそうなガラス細工のようだった。
「ねぇ、名前」
夕焼けが帰り道を茜色に染め上げる頃、公園で、俺は漸く声を絞り出すことができた。言葉にするまで、どれ程までに逡巡しただろう。
「もし、怖い夢を見た時は、ちゃんと言ってほしい。……俺が、全部受け止めるから」
それは誓いにも似た言葉だった。俺のセッターとしての役割のように、彼女の抱える不安や恐怖を、正確に、そして優しく受け止めたい。
名前はベンチの前で、ぴたりと立ち止まった。夕陽に照らされた彼女の表情は、どこか神々しい程に美しく、切なかった。やがて、ふわりと、蒲公英の綿毛が風に乗るように柔らかく微笑んだ。
「……じゃあ、宝石箱の鍵、京治くんに預けてもいい?」
その瞬間、俺はたぶん世界で一番間抜けで、無防備な顔をしていたと思う。
心臓が試合終了間際のラストプレーのように、馬鹿みたいに激しく高鳴り始めた。呼吸の仕方すら忘れ、浅い息を繰り返す。ああ、まただ。思春期特有のこの現象が、嫌になる程の露骨さで、俺の身体を強烈に支配する。名前を想う度に、俺はこうして自分自身に翻弄されるのだ。
「……うん、預かる。絶対、失くさない」
声が震えるのを抑えようと必死だった。その鍵は、ただの鍵ではない。名前の心の一部を、俺に委ねるという意味なのだから。
「うん。宜しくね、京治くん」
そう言って、名前は俺の手に、そっと自分の手を重ねた。指先だけを、ほんの少しだけ触れ合わせるように。彼女の指は驚く程に冷たかったけれど、その奥には確かな温もりが宿っていた。
その手の微かな温度だけで、俺はその夜、また別の夢を見た。
今度は――名前が心の底から楽しそうに笑っていた。日溜まりの中で、花々に囲まれて。
俺はあの忌まわしい怖い夢の代わりに、その宝石箱の中に、彼女の輝くような笑顔をそっと詰め込んだ。
俺だけの、誰にも渡さない、掛け替えのない宝物として。
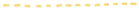 ほんの少しの不安が、心の底で炭酸水の泡のように、ぱちり、ぱちりと弾けては消える。
怖い夢なんて、もうとっくに見慣れていると思っていた。幼い頃は病弱で、一人で過ごす夜が多かったわたしにとって、それは日常の延長線上にあるものだったから。
けれど、今朝見たそれは妙に生々しく、粘着質な蜘蛛の糸が絡み付くようで、頭から離れてくれなかった。
京治くんが、わたしの名前を呼ぶ声がした。切羽詰まったような、焦燥に駆られた声。
わたしはそれに応えたいのに、声が出ない。金縛りにあったように身体も動かせないまま、どこか暗くて冷たい、知らない場所へずるずると引き摺り込まれていくような感覚。
あの瞬間の、心臓を鷲掴みにされるような恐怖を、もし彼に知られたら、きっと困らせてしまう。彼の眉間に、心配の色を浮かべさせてしまう。そう思った。
だから、わたしはいつものように、それを宝石箱に仕舞った。
幼い頃、兄貴兄さんに貰った、小さなオルゴール付きの宝石箱。
リボンが少し解れたアンティーク調の布張りのそれは、蓋を開けると音の掠れたショパンのノクターンが微かに流れて、わたしの小さな秘密を優しく閉じ込めてくれる。
だけど、京治くんはわたしの纏う僅かな沈黙の気配に、聡明な彼らしく、すぐに気づいてしまった。
授業中も、昼休みも、ずっと彼の視線を感じていた。
彼の視線は鋭くて、けれど、どこまでも優しい。オーボエの音色みたいに混じり気なく真っ直ぐで、それでいて包み込むような温かさがある。その視線に射抜かれる度、わたしは少しだけ息苦しくなり、同時に不思議な安心感に包まれるのだった。
放課後、彼に手を引かれて、いつもの帰り道から少し外れた、静かな公園に連れていかれた。夕暮れ時の公園には人影もなく、錆びたブランコが風に揺れて、キィ、と寂しげな音を立てている。風の音と、彼の低く落ち着いた声だけが、世界に二人きりしか居ないかのように、その空間を満たしていた。
「……うん、預かる。絶対、失くさない」
彼が紡ぐ言葉の一つひとつは、いつも誠実で嘘がない。丁寧に磨き上げられた黒曜石のように、曇りのない輝きを放っている。彼はそういう人だ。疑うことを知らない程、真っ直ぐな人。
わたしは思わず、彼が差し出した大きな手に、自分の指をそっと重ねていた。
小さな、けれど、とても確かな約束。
そう、こんな風に怖い夢なんて、京治くんの手指の温もりだけで、跡形もなく消えてしまえばいい。彼の体温が、わたしの不安を溶かしてくれるのなら。
わたしの宝石箱には、もう一つの夢を入れておくことにした。
京治くんと過ごす、これからの日々の夢。
それはきっと朝の光のように静かで、陽だまりのように暖かくて、時々、彼の不器用な優しさに照れ臭くなる程に甘く、そして、何度見ても飽きることのない、掛け替えのない大事な夢になるだろう。
全部、全部、その美しい夢の欠片を、わたしの宝石箱に大切に仕舞って、その鍵は、彼に預けておくのだ。
古来から伝わる、大切なお守りのように。
愛してる、京治くん。その想いも、今はまだ、この宝石箱の奥深くに秘めておこう。いつか、この鍵が本当の意味で、二人の心を繋ぐ日まで。
ほんの少しの不安が、心の底で炭酸水の泡のように、ぱちり、ぱちりと弾けては消える。
怖い夢なんて、もうとっくに見慣れていると思っていた。幼い頃は病弱で、一人で過ごす夜が多かったわたしにとって、それは日常の延長線上にあるものだったから。
けれど、今朝見たそれは妙に生々しく、粘着質な蜘蛛の糸が絡み付くようで、頭から離れてくれなかった。
京治くんが、わたしの名前を呼ぶ声がした。切羽詰まったような、焦燥に駆られた声。
わたしはそれに応えたいのに、声が出ない。金縛りにあったように身体も動かせないまま、どこか暗くて冷たい、知らない場所へずるずると引き摺り込まれていくような感覚。
あの瞬間の、心臓を鷲掴みにされるような恐怖を、もし彼に知られたら、きっと困らせてしまう。彼の眉間に、心配の色を浮かべさせてしまう。そう思った。
だから、わたしはいつものように、それを宝石箱に仕舞った。
幼い頃、兄貴兄さんに貰った、小さなオルゴール付きの宝石箱。
リボンが少し解れたアンティーク調の布張りのそれは、蓋を開けると音の掠れたショパンのノクターンが微かに流れて、わたしの小さな秘密を優しく閉じ込めてくれる。
だけど、京治くんはわたしの纏う僅かな沈黙の気配に、聡明な彼らしく、すぐに気づいてしまった。
授業中も、昼休みも、ずっと彼の視線を感じていた。
彼の視線は鋭くて、けれど、どこまでも優しい。オーボエの音色みたいに混じり気なく真っ直ぐで、それでいて包み込むような温かさがある。その視線に射抜かれる度、わたしは少しだけ息苦しくなり、同時に不思議な安心感に包まれるのだった。
放課後、彼に手を引かれて、いつもの帰り道から少し外れた、静かな公園に連れていかれた。夕暮れ時の公園には人影もなく、錆びたブランコが風に揺れて、キィ、と寂しげな音を立てている。風の音と、彼の低く落ち着いた声だけが、世界に二人きりしか居ないかのように、その空間を満たしていた。
「……うん、預かる。絶対、失くさない」
彼が紡ぐ言葉の一つひとつは、いつも誠実で嘘がない。丁寧に磨き上げられた黒曜石のように、曇りのない輝きを放っている。彼はそういう人だ。疑うことを知らない程、真っ直ぐな人。
わたしは思わず、彼が差し出した大きな手に、自分の指をそっと重ねていた。
小さな、けれど、とても確かな約束。
そう、こんな風に怖い夢なんて、京治くんの手指の温もりだけで、跡形もなく消えてしまえばいい。彼の体温が、わたしの不安を溶かしてくれるのなら。
わたしの宝石箱には、もう一つの夢を入れておくことにした。
京治くんと過ごす、これからの日々の夢。
それはきっと朝の光のように静かで、陽だまりのように暖かくて、時々、彼の不器用な優しさに照れ臭くなる程に甘く、そして、何度見ても飽きることのない、掛け替えのない大事な夢になるだろう。
全部、全部、その美しい夢の欠片を、わたしの宝石箱に大切に仕舞って、その鍵は、彼に預けておくのだ。
古来から伝わる、大切なお守りのように。
愛してる、京治くん。その想いも、今はまだ、この宝石箱の奥深くに秘めておこう。いつか、この鍵が本当の意味で、二人の心を繋ぐ日まで。