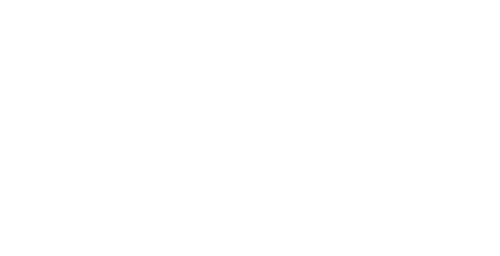……二人きりで過ごす夜の濃密な時間だけが、夫婦であることの証左ではない。
そんな当たり前のようでいて見過ごしがちな真実を、不意に、そして鮮やかに実感させてくれたのは、美術館で知的な刺激を受けた後の穏やかな午後のことだった。都心の喧騒を少し離れ、お気に入りのコーヒーショップへと向かう、緩やかな坂道の途中。
季節外れの暖かさを孕んだ風が、頬を優しく撫でていく。駅前の植え込みに咲くジャスミンの甘い香りがふわりと漂ってきて、午後の気怠い空気に溶けていった。隣を歩く名前は、例の鮮烈な赤い折り畳みヒールを履いている。出掛ける前、姿見の前で何度か軽やかにステップを踏み、「見て、京治くん。これで、どんな理不尽な戦場にも、赴けそうな気がしてきた」と、悪戯っぽく笑っていた顔が脳裏に蘇る。その真紅のヒールはアスファルトを小気味よく打ち鳴らし、彼女の背筋をいつもより少しだけ凛と見せていた。
しっかりと繋いだ手に、互いの体温が伝わる。美術館で見た抽象画について、或いは次に読みたい本について、取り留めなく言葉を交わしながら歩いていた、正にその時だった。
「……姉貴?」
不意に背後から掛けられた、記憶よりもやや低い、けれど聞き覚えのある声。反射的に振り返ると、そこには高校生くらいの男子が一人、やや着崩した制服でブレザーを片腕に掛け、もう片方の手には飲み掛けの缶コーヒーを持って、少し戸惑ったように立ち尽くしていた。
長めの前髪から覗く、どこか気怠げな、しかし、鋭い観察眼を感じさせる目元。姉である名前と通じる、独特の雰囲気を纏ったその少年を、俺は直ぐに認識した。
――名前の弟、弟くんだ。
声を掛けたはいいものの、弟くんは明らかに次の言葉を探しているようだった。その視線が、まず名前の足元、燃えるような赤のヒールに向けられる。次いで、俺と名前が繋いでいる手元へ。そして、最後に姉の顔をじっと見つめ、ややあってから、真顔でこう尋ねた。
「……お前、なにそれ。武器?」
余りにもストレート、且つ真剣な響きを帯びたその問いに、俺は思わず噴き出しそうになるのを堪える。しかし、言われた当の名前はと言うと、まるで長年、その質問を待ち望んでいたかのように、或いは全てを見通した修行僧のように静かな表情で、小さく首を傾げた。
「やっぱり言ったね、それ」
「いや、だって……そのヒール、トークで自慢してたけど、折り畳めるって、どういう構造してんだよ。意味わかんねぇ」
「踏み躙る為の、極めて合理的な発明だよ」
事もなげに、淡々と答える名前。そのシュールな返答に、弟くんは一瞬きょとんとし、それから訝しげに目を細めた。
「踏み躙るって、何を?」
「色々。例えば、過去の自分とか、つまらない他人の視線とか、今日のこの生温かい天気とか……」
「……後、元カレの理性とか、ですかね」
つい小声で付け加えてしまった俺に、名前は悪戯っぽく微笑み、繋いでいない方の手の指先で、俺の肘を軽く突いた。その仕草が妙に親密で、心臓が小さく跳ねる。
「元カレって、誰のこと?」
弟くんが怪訝そうに、俺を見る。
「今は夫だけど」
俺が訂正すると、名前が「ふぅん」と意味ありげな吐息を漏らした。
「じゃあ、その踏み躙られて砕け散った理性は、ちゃんと鞄にでも入れておいて。帰ったら、役に立つかもしれないから」
「それは……或る種の脅迫と受け取っても?」
「未来への期待、とも言うかな」
どこまでも噛み合っているようで、どこかズレているような、そんな俺達の不毛な会話に、弟くんはとうとう眉間に皺を寄せ、やれやれと肩を竦めた。
「……はぁ。まあ、今の姉貴が、そこそこ幸せだってのは分かったわ」
「弟くん。どうして、そう思うの?」
「だって、どうでもいい、くだらないことで会話がスムーズに成り立ってる時の姉貴は、大体、機嫌がいい証拠だから」
この弟、恐るべし。姉の生態に関する理解度が深過ぎる。名前は観念したように、小さく肩を竦めてみせた。
「弟は、わたしの取扱説明書の主席編纂者だからね」
「それよりさ、そろそろその最終兵器、解除したらどうだ? どう見ても足、痛そうだけど」
弟くんの鋭い視線が、再び名前の足元へ注がれる。午後の陽光を浴びて、赤いヒールはまるで警告色のように、アスファルトの上で鮮やかに照り返していた。
「……うん。正直、ちょっと、痛いかも」
あっさりと白状した名前に、俺は内心で小さく笑った。以前なら、弟の前でも見栄を張って強がったかもしれない。けれど、今は素直に弱音を吐けるだけの穏やかさが、彼女の中にあるのだろう。それは、俺達の関係性が育んできた、ささやかな変化なのかもしれない。
「じゃあ、そこのベンチで少し休みますか。俺、冷たいものでも買ってきますよ。アイスコーヒーでいい?」
「……ありがとう、京治くん。助かる。じゃあ、わたしはこれを……折り畳むね」
名前はそう言うと、ベンチに腰を下ろし、少し顔を顰めながらも、慎重な手つきで足首のストラップを外し始めた。そして、まるで大切な儀式のように赤いヒールを脱ぎながら、独り言のように、けれど、俺達に聞かせるように続けた。
「靴も、見栄も、意地っ張りな強がりも――ちゃんと丁寧に折り畳んでおけば、また必要な時に、綺麗に広げられるからね」
それは日々の忙しさの中に埋もれて忘れがちな、けれど、とても大切な、ささやかな人生の知恵のように聞こえた。
俺は「じゃあ、すぐに戻ります」と二人に言い残し、急いで缶コーヒーを買いに行くフリをして、ほんの少しだけゆっくりと歩き出した。
振り返らずとも、背中に感じる姉弟の穏やかな空気。そして、俺自身の頬が、どうしようもなく緩んでいるのがわかった。
結婚して、幾つもの季節が巡り、互いの知らない部分など、もう無いと思っていたのに。この人は尽きることのない泉のように、新しい言葉で、予想外の仕草で、俺の心の琴線を毎日、少しずつ、確実に揺らしてくる。
夜の静寂の中だけで交わされる熱だけが、絆の全てじゃない。
こうして、午後の柔らかな光の中で、互いのちょっとした意地や、弱さや、可笑しみを見せ合い、笑い合い、そして受け止め合うこと。そんな何気ない時間の積み重ねこそが、俺と彼女の"夫婦"という形をより深く、豊かなものにしていくのだろう。
――きっと、俺は今日もまた、この予測不能な人に翻弄され、その度にどうしようもなく心を奪われ、深く惚れ直すのだ。
何度でも。この日常という、愛すべき戦場で。