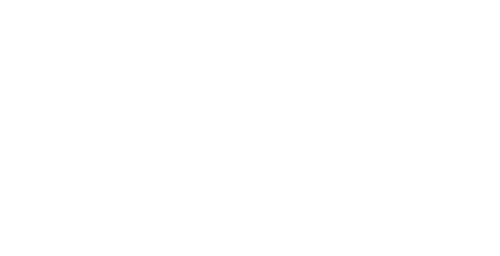茜色が世界を塗り替える時間。燃えるような夕陽が、西日に傾いた校舎の窓ガラス一枚一枚に、溶け込むように沈んでいく。その光は長く影を引き、放課後の喧騒が嘘のような静寂だけが、埃の匂いと共に古い音楽室を満たしていた。
部屋の奥、長い間、誰にも触れられていないであろうアップライトピアノの前に、彼女は居た。
苗字名前。
俺の、恋人。同じクラスで隣の席に座り、穏やかだった筈の日常に鮮やかな彩りを与え、そして……人生で初めて、"恋"という言葉が持つ、甘く切ない輪郭を教えてくれた人。
艶やかな髪が、白いブラウスの肩に沿って滑り落ちる。陶器のように白い指先が、黄ばんだ鍵盤の上にそっと置かれていた。触れるか触れないかの、絶妙な距離で。
けれど、彼女は音を紡ごうとはしなかった。
その姿は――ひどく儚く、捉えどころがなく……そう、まるで、そこに在る筈のない何か、形のない"空虚"そのものを、そっと掬い上げようとしているかのように見えた。息をすることさえ躊躇われるような、張り詰めた静けさが彼女を包んでいた。
「……名前、弾かないの?」
絞り出した声は、思いの外、掠れていた。呼び掛けると、名前は緩慢な動作でこちらを振り返る。吸い込まれそうなほど深い、深海の底を思わせる凪いだ瞳が、俺を真っ直ぐに見つめた。その瞳の奥に揺らめく感情を、俺はまだ読み取ることができない。
「今日は、音を聴くよりも、この沈黙の方が……深く響く気がするの」
紡がれた言葉は、まるで詩の一節のようだ。その真意は、すぐには掴めない。けれど、分からないからこそ、目を逸らすことなんてできなかった。
――この、どこか掴みどころのない、それでいて核心を突くような不思議な引力。それが、俺が名前に惹かれた最初の理由だったのだと、こういう瞬間に出会う度、何度でも思い出す。
「ねぇ、京治くん」
静寂を破ったのは、再び名前の声だった。
「わたしって、ちゃんと"ここ"に居るのかな?」
その問い掛けに、心臓が微かに跳ねる。
「……どこか、行くつもり?」
「ううん、そうじゃなくて」
名前は小さく首を振る。
「わたしね、時々、自分が誰かに"触れられている"っていう感覚を、忘れてしまう時があるの。まるで自分が、透き通った空気か何かみたいで……誰の手も、わたしを通り過ぎていくような、そんな感じ」
努めて冗談めかして言ったのだろう。けれど、その声色には隠し切れない寂寥感が滲んでいて、俺の胸の奥を、細い針でちくりと刺すような痛みが走った。
普段はどこまでもマイペースで、掴みどころがなく、現実から少しだけ浮遊しているような名前が、こんなにもはっきりと不安を口にするなんて――その事実そのものが、俺をどうしようもなく焦らせた。
不意に、脳裏を過る。
最近の練習試合での、自分のトスの、ほんの僅かなズレ。
木兎さんのあの独特なテンションの波を、上手く捉え切れなかった瞬間の焦り。
急激に変化していく身体の成長に、まだ心が追いついていないような、妙な違和感。
それは、指先で確かな感触を求めているのに、何度伸ばしても空を切るような、もどかしい感覚。
目の前に"正解"がある筈なのに、どうしてもその実体を手繰り寄せられない。
その感覚は、驚く程、今の名前が抱える不安と、そして、俺達の関係性そのものに重なる気がした。俺は名前に、ちゃんと触れられているのだろうか。俺の気持ちは、本当に彼女に届いているのだろうか。
「……俺は、名前に触れてるよ」
言葉を探すように、ゆっくりと紡ぐ。
「今も。昨日だって。……いや、もっとずっと、前から」
「本当に?」
「うん。ほんと。名前は空気なんかじゃない。幽霊でもない。ちゃんと、ここに居る。俺の隣に」
そう言って、俺は震える彼女の左手に、そっと自分の右手を重ねた。
象牙のように滑らかで、少し冷たい指先が、驚いたようにぴくりと震える。そして、迷うような間を置いて、彼女の指が、壊れ物に触れるように、そっと俺の手を握り返した。
伝わってくる、か細いけれど確かな温もり。その熱が、俺の心臓を不規則に跳ねさせる。
――まただ。
この、心臓が直接掴まれたような感覚。これは、普通の男子高校生にとっては、余りにも不可抗力で、反則的な現象だと思う。平静を装うのに必死で、呼吸が少し浅くなる。
「京治くん」
「……ん?」
「わたしも……わたしも、ちゃんと京治くんに触れている?」
問い返す声は、少しだけ震えていた。その健気さが、また胸を締め付ける。
「……当たり前だろ」
少し照れが混じるのを隠せずに、視線を落としながら答える。
「もう、毎日、過剰なくらいだよ。名前に不意に触れられる度に、俺の心臓は幾つあっても足りない」
正直な気持ちを、少しだけ誤魔化すように早口で告げると、名前は、ふっと息を吐くように目を細めて、柔らかく微笑んだ。花の蕾がゆっくりと開くような、そんな笑顔だった。
「ふぅん……そうなんだ。じゃあ、もっと触れようかな」
悪戯っぽく、それでいて確信を帯びた声で、名前は言う。
「だって、空虚を掴もうとしていたのは、どうやら、わたしだけじゃなかったみたいだから」
その言葉に、心臓を見透かされたように、どきりとした。
彼女は、俺が思っている以上にずっと鋭敏で、聡明だ。
俺の中に巣食う、セッターとしての自信の揺らぎや、拭えない焦燥感、そして、スター選手達の影で感じる、どうしようもない劣等感――そういう、言葉にしてこなかった澱のような感情を、彼女はまるで当然のように見抜いている。
「……参ったな」
思わず、乾いた笑いが漏れた。
「なにが?」
「いや……名前の方が、俺なんかよりもずっと冷静で、大人だって思ってたけど……。多分、君の方が、ずっと感情の波が大きいんだね」
「うん、そうかも。わたし、多分、感情だけで生きているから」
名前はこくりと頷く。
「だから、心が空っぽになると、すぐに悲しくなってしまうの。京治くんが隣に居てくれても、ちゃんと触れられていないような気がすると、……泣きそうになる」
――そんな時は、すぐに教えてくれ。
俺が何度でも、その手を強く握り直すから。名前がここに居るって、俺が君を見ているって、分かるように。
そう言おうとしたのに、言葉は喉の奥で形に成らずに消えた。もどかしい。けれど、今は言葉よりも確かな何かが必要な気がした。
代わりに、俺は重ねたままの彼女の手を、そっと自分の口元へと引き寄せた。そして、白く細い薬指の付け根辺りに、祈るように、一つ、小さなキスを落とした。
「……わ、っ」
名前が息を呑む気配が伝わる。顔が熱い。自分でも驚くほど大胆なことをしてしまった自覚があった。
「……煩い。こっちが恥ずかしいんだから、黙ってて」
耳まで赤くなっているであろう自分を隠すように、ぶっきら棒に言うと、名前はくすくすと、鈴を転がすように笑った。
「今ね、京治くんのこと、凄く好きだって思った」
「……っ、それを言う方が、よっぽど恥ずかしいだろ……」
名前が、今度は声を立てて笑った。
つられて、俺も笑っていた。
さっきまでこの部屋を支配していた、あの息苦しい程の空虚は、もうどこにも感じられなかった。夕陽の最後の光が、ピアノの黒鍵を鈍く照らしている。
互いの指をもう一度、しっかりと絡め合わせる。伝わる温もりと、確かな存在感。
古びた音楽室の片隅で、俺達は、不確かで掴みどころのなかった筈の"恋"という感情の、その確かな形を、今、漸く二人で掴んだような気がした。