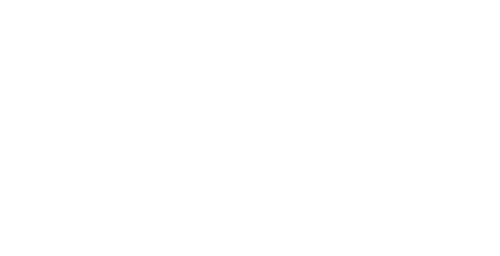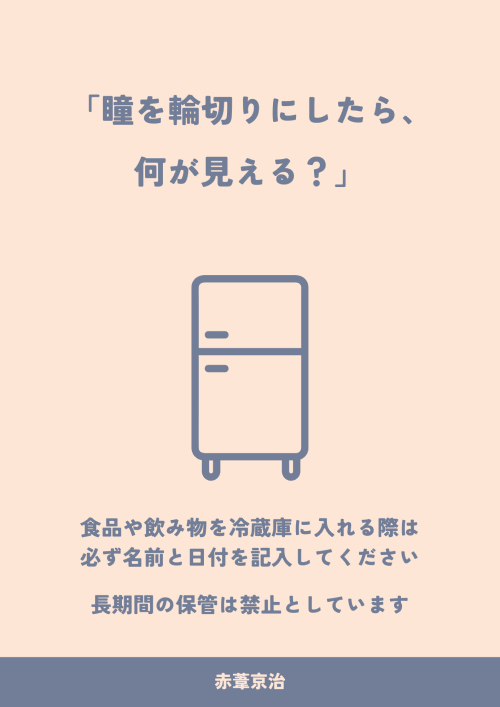
放課後の美術室は、油絵の具と埃の匂いが混じり合った、独特の空気に満ちていた。西陽が大きな窓から斜めに差し込み、床に長い光の帯を描いている。その光の中で、俺――赤葦京治は、目の前の作業台に並べられた異様なオブジェに、言葉を失い掛けていた。
「これは……その、目、ですよね?」
恐る恐る尋ねると、隣に立つ彼女――苗字名前は、事もなげに頷いた。
「うん、そう。"愛"を"目"に見立ててみたの。だから、これは"アイの輪切り"」
意味が分かるような、分からないような。いや、正直に言えば、殆ど分からない。けれど、それが苗字名前という人間の創り出す世界の常だった。彼女の思考回路は、常人には計り知れない深淵を覗かせることがある。何を考えているのか、その真意はどこにあるのか、正確に理解できた試しはない。
ただ、分からなくても――どうしようもなく、惹かれてしまうのだ。
作業台の上には、まるで本物の眼球をスライスしたかのような、グロテスクな程にリアルなガラス製のオブジェが、幾つも無造作に並べられている。その一つひとつは、透明なガラスの中に、幾重にも重ねられた深紅の花弁――恐らくは薔薇だろう――のような彩色が施され、妖しい光を放っている。そして、その中心部には、よく見なければ気づかないほど微かに、しかし確かに、ハートの形が彫り込まれていた。美しさと不気味さが、危ういバランスで同居している。
「これ、今年の文化祭の美術部展示に出そうと思っているんだ」
名前は、まるで子供が秘密の宝物を見せるかのように、少しだけ声を弾ませて言った。
「……いえ、まあ、美術部の展示作品としては、非常に斬新で、独創的だとは思いますけど……」
正直な感想を言えば、少し、いや、かなり怖い。これを一般の生徒達が目にして、どんな反応をするだろうか。想像するだけで、胃がきりりと痛む気がした。けれど、この奇妙なオブジェについて説明する時の名前の瞳が、普段の彼女からは想像もつかない程、きらきらと嬉しそうに輝いていたから、否定的な言葉を口にすることはできなかった。
ガラスの眼球に灯る赤色が、夕陽を受けて、彼女の白い頬にも淡く反射している。その光景に、俺はふと、逸らしていた視線を彼女へと戻した。
目が合った。名前の視線は、いつからか、真っ直ぐに俺に向けられていた。深い、深い、夜の湖のような瞳。その奥に何が隠されているのか、読み取ることはできない。ただ、じっと、俺を見つめている。
「京治くん」
静かな声が、俺の名前を呼んだ。
「わたしのこの瞳も、輪切りにしてみたい?」
「……え?」
瞬間、思考が完全に停止した。まるで時間が止まったかのように、周囲の音が遠退く。心臓が、肋骨の内側で一度、大きく跳ね上がった。ドクン、ドクン、と自分の鼓動が、耳の奥でやけに煩く響いている。輪切り? 彼女の、この美しい瞳を?
「ううん、冗談だよ」
俺の動揺を見透かしたように、名前はふっと息を吐くように笑った。けれど、その目は笑っていない。
「ほんの少しだけ、怖がらせてみたかっただけ。ねぇ、京治くん。愛って、時々、凄く残酷なものだと思わない?」
口元だけで弧を描くその表情は、どこか人間離れしていて、古い絵画に描かれた吸血鬼を連想させた。月光の下で微笑む、美しくて、儚げで、それでいて血の匂いを纏う夜の姫君――そして、そのミステリアスで少し危険な姫君は、紛れもなく、俺の恋人なのだった。
「……その冗談は、多分、木兎さん辺りには、全く通じないと思いますよ」
どうにか平静を装って、少しズレた返答を試みる。これ以上、彼女のペースに巻き込まれてはならない。
「そう? じゃあ、今度、弟にでも言ってみようかな」
「それは絶対にやめてください。弟くんは多分、本気で引きます」
俺の必死の訴えが、どうやら彼女の琴線に触れたらしい。ふふ、と名前が堪え切れないように、今度は本当に楽しそうに笑った。強張っていた口元の緊張が解け、少女らしい柔らかな表情が覗く。その笑顔を見られただけで、なんだか今日一日が、とても価値のあるものになったような気がした。単純だと自分でも思うが、仕方ない。
ほんの少しの間、沈黙が落ちる。
夕暮れの赤い光が、美術室の大きな窓ガラスを通して、舞台照明のように名前の横顔をドラマティックに照らし出していた。埃っぽい空気の中で、彼女の細く柔らかな髪が、光を受けて金色に煌めき、作業台に置かれたガラスの眼球に反射して、ゆらゆらと揺れている。その光景は、非現実的なほど美しかった。
「京治くんは」
不意に、名前が口を開いた。その声は、余りに唐突で、余りに静かだった。
「わたしの、どこが好きなの?」
名前の声はいつもそうだ。抑揚がなく、平坦に聞こえるようで、その実、言葉の奥底には、計り知れない程の感情が、静かに、けれど確かに揺らめいている。
俺は答えようとして、しかし一瞬、言葉に詰まった。好きなところ――そんなもの、挙げ始めたらキリがない。「全部」なんて、月並みで陳腐な言葉では、この感情を表すには到底足りない。でも、具体的にどこが、と問われると、一つに絞るのもまた難しい。
考えあぐねた末、最初に心惹かれた部分を口にした。
「……目、ですかね」
「目?」
「はい。最初に、強く引き込まれたのが、名前さんの目でした。夜の闇みたいで、どこまでも深くて……何を考えているのか、全然分からないのに、どうしても目を逸らすことができなかった。多分、今でもそれは変わりません」
言いながら、少しだけ照れ臭いような、気恥ずかしいような気持ちが胸を過る。けれど、これは紛れもない本心だ。初めて図書室で名前を見掛けた時、文字通り、その不思議な瞳に視線が絡め取られて、動けなくなったのだ。それが、この厄介で、けれど愛おしい恋の始まりだったのだと、今ならはっきりと断言できる。
「ふぅん……」
名前は面白そうに目を細めた。
「じゃあ、わたしも、京治くんのその綺麗な目を、輪切りにして、じっくり観察してみたいな。わたしのことが、どれくらい、どんな風に映っているのか、確かめてみたいから」
背筋がぞわっと粟立つような、それでいて、どこか甘美な響きを伴う台詞だった。それが彼女なりの愛情表現なのか、それともまた悪趣味な冗談なのか、判別がつかないのも、実に彼女らしい。
でも――そんな風に言われてしまっては、俺の中の、まだ青臭い部分が、どうしようもなく反応してしまう。思春期特有の、コントロール不能な生理現象を、またしても自覚する羽目になった。マズい、と内心で焦る。
俺の内心の動揺など露知らず、名前は俺の目の前にすっと立つと、くるりと優雅に踵を返し、近くにあった椅子の背に、軽く凭れ掛かった。そして、白く細い、陶器のような指先が、するり、と伸びて、俺が着ている制服のブレザーの袖を、そっと摘まんだ。
「わたしの中の京治くん、最近、なんだかどんどん大きくなって、いっぱいになってきてしまって。このままだと、溢れてしまいそう。だから――そろそろ、ちゃんと、冷蔵庫に保存しておこうかなって思ってる」
「……俺、いつの間にか生もの扱いですか?」
思わずツッコミを入れると、名前は首を横に振った。
「ううん。とっても大事にしたいから。腐らせたり、ダメにしたくないの」
名前が紡ぐ言葉は、時折、鋭い棘を隠し持っている。けれど、その棘は、誰かを故意に傷付ける為のものではなく、寧ろ、不器用な彼女が自分自身を守る為に纏った鎧のようなものだと、俺は理解しているつもりだ。だから、俺はその棘ごと、彼女の全てを、この両手でしっかりと受け止める覚悟を決めたのだ。
輪切りにされたって構わない。それが、彼女からの愛の証だと言うのなら、喜んで差し出そう。
「……じゃあ、その冷蔵庫、俺も一緒に入りたいんですが、まだ空きスペースはありますか?」
冗談めかして、けれど本気で尋ねる。
「うん。勿論」
名前は悪戯っぽく微笑んだ。
「京治くんの為なら、いつでも特等席を空けてあるよ。隣には、このガラスの"アイ"達も一緒にね」
そう言って悪戯っぽく笑う名前に、俺はもう、完全に、白旗を上げるしかなかった。降参だ。
夕暮れの美術室。ガラスの眼球に見守られながら、俺の思春期の心臓は、今日も今日とて、忙しなく鳴り続けている。
あの『アイの輪切り』が、俺の脳裏で、いつまでも、ぐるぐると回り続けていた。